DRAMをどう使うか? ――性能の改善技術とその性能を生かす選択方法
2)内部バスの反転速度(コア速度)
SDR→DDR-I→DDR-IIと続くSDRAMの世代交代はデータ転送速度の倍増をもたらしましたが,その副産物としてバースト長(burst length)の増大があります.微細化に伴って内部バス配線の線幅は細くなり(配線抵抗が増大する),配線間隔は狭くなる(線間容量が増大する)ので,DRAM内部バスの反応速度(コア速度)の大幅な改善は困難となります.
このため,従来の倍の速度でデータを入出力するためには,内部バスを従来の2倍の数だけ並列に動作させ,入出力ポートでパラレル-シリアル変換して2倍の速度のデータ列を得る必要があります(図9).実際,DDR-I SDRAMでは2:1のパラレル-シリアル変換(2ビット・プリフェッチ)が,DDR-II SDRAMでは4:1のパラレル-シリアル変換(4ビット・プリフェッチ)が用いられています.
プリフェッチ・ビット数の増大は,入出力されるデータ列の長さ,すなわち最小バースト長の増加をもたらします.最小バースト長は,SDR SRAMでは1,DDR-I SDRAMでは2,DDR-II SDRAMでは4となっています.さらに,高速のDDR-III SDRAMにおいても同様で,最小バースト長を8とすることが検討課題となっています.バースト長の増大は,CPUなどとDRAMの間で授受するデータの最小単位の増大を意味し,機器によっては採用が困難となる可能性があります.
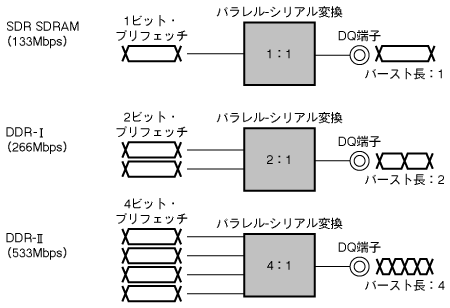
〔図9〕プリフェッチ・ビット数の増大でデータ転送速度を高速化
同一のコア速度(133MHz)でそれぞれの規格を比較したものである.DDR-Iでは,内部バスと外部データ・ポートとの間に2:1のパラレル-シリアル(P-S)変換が存在する.DDR-IIでは,4:1のP-S変換が存在する.一つのデータ・ポートに対して同時並列に動作させる内部バスの数がn の場合,この構成をn ビット・プリフェッチという.このプリフェッチ・ビット数を倍増させることでデータ転送速度の向上を図っている.


