DRAMをどう使うか? ――性能の改善技術とその性能を生かす選択方法
●独自の路線を歩むナロー・バス技術「Rambus」
情報処理機器に用いられるDRAMの中で,JEDEC標準のものと対極をなすのが「Rambus(ラムバス)DRAM(以下RDRAMと略記)」です.Rambusシステムは,×16/18ビット・バス幅のナロー・バス(Rambus Channel)を基本構成とし,その超高速動作によって高いバンド幅(800Mbps~1,066Mbps)を得ています.この特徴から,RDRAMは最上位のパソコンやネットワーク機器などに幅広く用いられています.
Rambusシステムの特徴は,その同期化手法にあります(図12).クロック配線を折り返し,その伝搬の向きによってクロックを書き込み用と読み出し用に分けます.そして,データの伝搬方向とクロックの伝搬方向をそろえます.この手法によって,ストローブ信号が不要となります.
そのほかの特徴として,アドレス信号と制御信号の伝送にパケット化した通信手法を用いてピン数の削減を実現している点が挙げられます.また,Rambusシステムはバス幅とDRAMの構成が一致しているので,増設単位(granularity)がDRAM1個分でもよいという特徴があります.少ないピン数や小容量の増設が可能といった特徴から,RDRAMは組み込み機器向けとしても高い可能性を持っています.
Rambus社は,RDRAMの1,333Mbpsまでの性能向上や,Rambus Channelを複数組み込んだモジュールの開発,さらに3.2Gbps以上のデータ転送速度をカバーする「Yellowstone」と呼ぶ新しいメモリ・インターフェース技術の開発を行っています.Yellowstoneは,データ・ピンごとのタイミング調整機能を持っています.
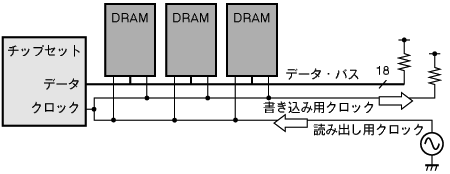
〔図12〕Rambusシステムにおけるデータ授受方式
折り返したクロック配線を読み出し(read)用と書き込み(write)用に分けて活用する.どちらの動作モードでもデータ伝搬方向とクロック伝搬方向が一致する.


