DRAMをどう使うか? ――性能の改善技術とその性能を生かす選択方法
1.主な市場は情報,ディジタル,通信,FA
図1に,向こう1~2年の機器別DRAM採用動向の予測を示します.DRAM市場は,次に示すように大きく4種類に分けられます.こうした市場からは個別のシステム要求が出されており,それらに対応するDRAMの機能や性能も多様なものとなっています.
1)パソコン,WS,サーバなどの情報処理機器市場
パソコンやワークステーション,サーバなどの情報処理機器の市場では,DRAMの採用条件としてセカンド・ソース(オリジナルのICと同一の機能と同一のピン配置で作ったもの)の存在が必須となっています.このため,独自規格の製品は採用される可能性が低く,JEDEC(Joint
Electron Device Engineering Council)注1標準のDRAMを中心に採用されています(JEDEC非標準のRambus DRAMについては別の項で述べる).
情報処理機器の市場では,処理データ量の増大,プロセッサの高速化,装置寸法の制限(許容発熱量の制限)という条件から,DRAMには「大容量」,「高速」,「低消費電力」といった相反する要素が同時に求められます(コラム「メモリの容量と速度の表現方法」を参照).
注1;正式名称はJEDEC Solid State Technology Association.EIA(Electronic Industries Alliance)に属する組織であり,半導体技術の標準化を行っている.ホームページのURLは「http://www.jedec.org/」.
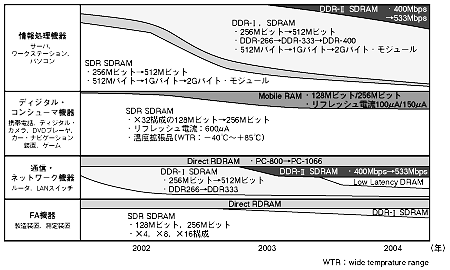
〔図1〕市場分野別のDRAM採用動向
DRAMの市場を大きく四つに分類して,それぞれの市場における採用比率動向の実績と予想を示した.情報処理機器市場ではDDR-Iが当面の主流となり,その後にDDR-IIへの移行が控えている.ディジタル・コンシューマ機器市場では,SDR SDRAMとSDR SDRAMの低電圧・低消費電力版であるMobile RAMが主力であり,DDR-Iへの移行時期は2004年以降になると見られる.通信・ネットワーク機器市場ではDirect RDRAM(Rambus DRAM)やDDR-I/II,さらには非標準の高速DRAM(図中ではLow Latency DRAMという一般名称で記した)など,多様な製品群が共存すると考えられる.その理由として,性能を最優先する機器とコスト・パフォーマンスを優先して標準品を採用する機器が同じ市場に存在することが挙げられる.FA機器は,ほかの市場に比べて緩やかな移行傾向を示す.


