DRAMをどう使うか? ――性能の改善技術とその性能を生かす選択方法
4)高速動作におけるデータ授受手法の変化
プリント基板上では,信号の伝搬遅延はおよそ6~7ps/mmの値を持ちます.通常のパソコンの基板寸法を想定してチップセットからメモリ・モジュール上のDRAMまでの配線長を150mmとすると,この配線の伝搬遅延時間は約1nsとなります.つまり,チップセットから出たクロックがDRAMに届くまで1nsかかります.そして,到着したクロックを基準としてDRAMがデータを出力し,それがチップセットに届くためにも1ns必要となります.したがって,合わせて2ns程度のオフセットが読み出し時に生じます.SDR SDRAMが133Mbps(クロック周期7.5ns)の読み出し動作を行っている場合,7.5nsのデータ周期に対するオフセットの比率は3割程度になります.これが同じクロック周期で動作するDDR-266(DDR-I SDRAM,266 Mbps動作)になると,データ周期3.75nsの半分以上がオフセットとなります.さらにワイド・バスの各配線長差や並列動作中のDRAMの特性差など,タイミングの不確定要素の影響が,高速化に伴って相対的に大きくなります.
これを避けるため,データの送り手が基準信号も同時に送信するソース・シンクロナスの手法が採用されました.これがデータ・ストローブと呼ぶ信号の導入です(図11).このストローブ信号を基準にして,受け手はデータを受信します.この手法はDDR-I,DDR-IIの両SDRAMに採用されています.
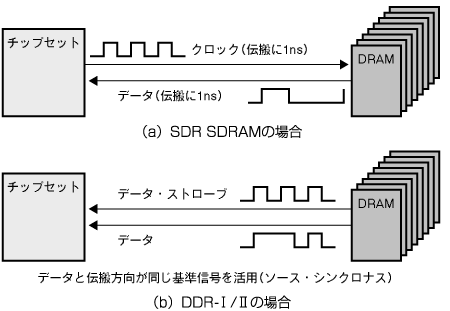
〔図11〕データ授受方式の変化
SDR世代までは読み出し時の基準クロックの伝搬方向とデータの伝搬方向が逆であったが,DDR世代からはデータの伝搬方向と一致した基準信号(データ・ストローブ)を用いるようになった.データの送り手が基準信号の発信者になる(ソース・シンクロナス).


