設計の基本は仕様の理解 ――高速シリアル通信を実現するために知っておくべき最低限の知識
●最近ではほとんどのパソコンが標準装備
USB 2.0は2000年4月27日に制定されました.USB Imple-menters Forum(USB-IF)のホームページ(http://www.usb.org/)を参照すると,開発の際に必要となるほとんどの情報を入手できます(図7).
USB 2.0規格は米国Intel社が中心となって作成されました.日本企業としてはNECが最初のハイスピード・モード対応のホスト・コントローラを開発しました.このホスト・コントローラなくしては,USB 2.0規格の普及は難しかったと思われます.
Intel社のチップセット「The I/O Controller Hub4(ICH4)」にホスト機能が組み込まれてからは,ほとんどの新型パソコンはハイスピード・モードをサポートするようになりました(LSIメーカにとっては,規格制定からの約2年間はデバイスの認識や安定な通信との戦いだった).
安価なシールド・ケーブルを使用して480MHzの半2重通信とホットプラグ(活線挿抜)を実現できたのは,USB 2.0の規格書とその認証システムに負うところが大きいと考えられます.これらは,安定したハードウェアとファームウェアの動作を保証し,WindowsなどのOSが正しくデバイス・ドライバをインストールするのに重要な役割を果たしています.
機器開発者としては,480MHzが高周波であるという事実をきちんと認識しておかなくてはなりません.高周波であるがゆえに,例えばUSBデバイスのバイパス・コンデンサ(パスコン)は,受信データからのクロック・リカバリやデータ送信のクロック生成に使用するPLLのジッタ特性に重大な影響を与えます.信号線D+,D-のインピーダンスは,線間とグラウンドの間の両方について必ず規格内でなければなりません.これを守らないと複数のパソコンと安定した通信を行えません.また,ハイスピード・モード対応のプリント基板は必ず4層以上とし,LSIメーカの推奨するパターン・レイアウトに従います.独自の回路を設計する場合には,伝送線路理論に関するアナログ的な知識が必要となります.
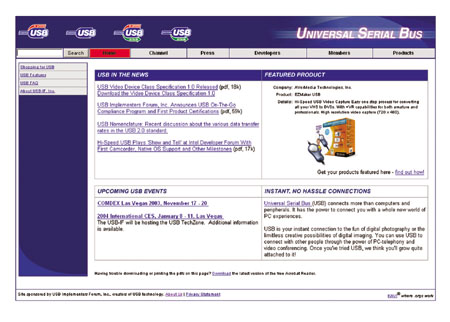
〔図7〕USB-IFのホームページ
USBの設計開発に必要なほとんどの情報がここから入手可能.
URLは「http://www.usb.org/」.


