電子機器開発者のための半導体パッケージ熱設計入門 ――待ったなし!SOC & SIPの熱対策
したがって,ASICデバイスの発注時に,システム設計側で最大稼働状態においてトランジスタの何%が稼働するかを把握できない場合,安全をみて最大消費電力を高めに設定して計算することになります.その結果,熱抵抗として過度に小さな値が要求され,高価なパッケージを選択せざるをえない場合もあります.また,汎用製品の一つであるCPUなども,システム側における使われかたによって実際の最大消費電力が異なるので,半導体メーカとしてはマージンをとってパッケージを設計することになります.
電子機器メーカが想定する機器内の雰囲気温度Taは,「対象電子デバイスからの影響を受けない十分に離れた位置での空気温度」と定義されています.そして,その温度をベースとして半導体デバイスの接合温度が動作保証温度以下になるように設計します.しかし,実際に電子部品がぎっしりと詰め込まれたプリント基板上の雰囲気温度を測ろうとした場合,部品から離れ過ぎると,実際の雰囲気温度というよりも室温に近くなります.一方,部品に近づけば,デバイス自身の温度上昇の影響を受けてしまいます(図14).つまり,雰囲気温度とは,「パッケージの熱設計のために想定された,現実には測定できない温度」ということになります.
このように,パッケージに要求される熱抵抗θjaを導き出すための前提条件は不確定なものが多いため,結果として過度のマージンをもつ高価なパッケージを採用する場合があります.
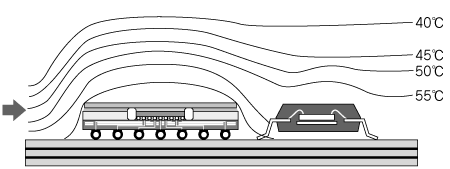
図14 雰囲気温度とは?
自己発熱の影響を受けず,周囲のデバイスによる温度上昇を見込んだ温度が雰囲気温度だが,図の右側のQFPの雰囲気温度は,いったいどの温度を指すのだろうか?


