プログラマブル・ロジックを集積したSHマイコンのすべて(前編) ――FPGA/PLD市場に参入する日立製作所の取り組み
1)組み込み用マイコンと標準ロジックICによる設計
このケースでは,自分のシステムに適合したマイコンがなかなか見つからず,外付け部品を多用して,コストの増大を招いてしまうことがある.
2)組み込み用マイコンとFPGA/PLDによる設計
この場合,開発期間を短くできるという長所がある.また,最近のFPGA/PLDには,小規模のゲートアレイの置きかえをねらっているものもあり,選択肢が多い.しかし,FPGA/PLDをマイコンに外付けする場合,FPGA/PLDとマイコンの間のバス・インターフェースを設計する必要がある.また,その分FPGA/PLD内のリソースを消費してしまう.FPGA/PLD内に実装するレジスタなど,CPUからアクセスするリソースが多いと,図2のようにFPGA/PLDの動作周波数が低下してしまうことがある.マイコンとFPGA/PLDの2チップ構成になるため,基板面
積も増加してしまう.
3)ASICによる設計
このケースでは,動作周波数を向上させ,消費電力も低減することができる.低コストで所望の機能仕様を1チップ化することができる.しかし,機能設計から機能検証,タイミング検証,レイアウト設計,テストなど一連のLSI開発の工程を踏む必要がある.開発期間が長くなり,市場要求の変化に追いつけない場合がある.さらに今後,製造プロセスの微細化(0.13μmルール以下)によって,ウェハ前工程のマスク代やレチクル代,ウェハ加工費が増大する.大規模な生産数量を見込めないかぎり,開発費用を十分に回収できない可能性もある.
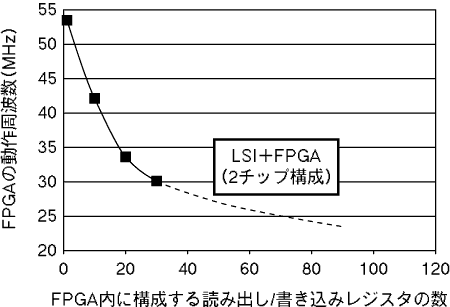
〔図2〕従来のFPGA/PLDの問題点
一般に,FPGA/PLDはその内部に構築する論理の規模が増大すると,内部の基本セル間を結ぶ配線が最適化されず,動作周波数が低下してしまうという問題点がある.規模の大きい論理をFPGA/PLD内に実現するとき,所望の動作周波数が得られず,設計の手戻りを強いられることが多い.


