つながるワイヤレス通信機器の開発手法(6) ――原理設計を行う 通信工学のおさらい
ここで,基本的な変調方式について説明する.図11の中で送信したい情報は音声とする.音声情報とオフセットを持たせたキャリアの掛け算を行うと,AM(amplitude modulation)変調信号を得ることができる.この動作は,増幅器の増幅利得を音声情報で変化させれば実現できる.しかし,最近では前述のとおりDSPやディジタル回路の乗算器,加算器を使って実現することが多い.
上記以外に,いくつかの変調方式を組み合わせた複雑な変調方式が存在する.地上波マイクロ回線やワイヤレスLANの規格の一つであるIEEE 802.11aに使われるQAM(quadrature amplitude modulation)はASKとPSKを組み合わせたものである.また,図9(d)で紹介しているBPSKは,PSKの一種である.このほかにも,一度に2値(2ビット)を送ることができるQPSK,3値を送ることができる8PSKなどがあり,いずれもワイヤレスLANなどに使われている(図12).これらの変調方式のどれを通信に使うかは以下のような観点から決められる.
- 変調,復調回路が簡単なこと
- ノイズに強いこと
- マルチパスに強いこと
- 消費電流が少ないこと
- 高速,広帯域の通信に対応できること
選んだ変調方式がこれらのすべてにマッチする場合もあるし,どれかを犠牲にし,どれかを優先する場合もある.
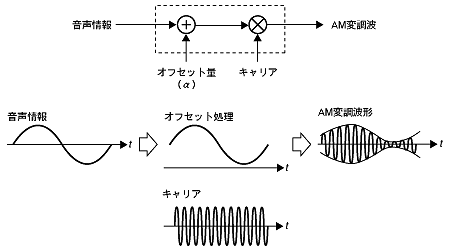
〔図11〕アナログ振幅変調(AM)
音声情報とオフセットを持たせたキャリアの掛け算を行うと,図のようなAM変調信号を得ることができる.
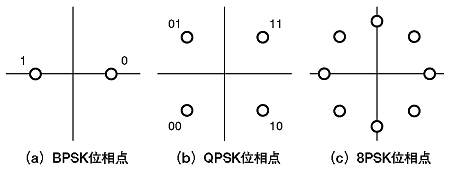
〔図12〕各種PSK方式
BPSKは,PSKの一種である.ほかにも一度に2値(2ビット)を送ることができるQPSK,3値を送ることができる8PSKなどがある.いずれもワイヤレスLANなどに使われている.


