ポストPC時代のキーワード「エンベデッド」のすべて ――転換点はカー・ナビゲーション・システム
●今後の主流はオンチップ・デバッグ
もっともモダンなデバッグ手法は,CPUにデバッグ機能と回路を内蔵し,そのオンチップ・デバッグ機能とホスト上のデバッガがやり取りをして,デバッグを可能にするものだ.こうしたオンチップ・デバッグ機能には,Motorola社が683xxシリーズやColdFireシリーズに内蔵したBDM(Background Debug Mode)がある.BDMはCPUのマイクロコードでデバッグ命令を実装し,専用のデバッグ・ピンを外部にもたせて,専用のケーブルでデバッガと交信する仕組みになっている.
今後はJTAGを利用する方法が主流だ.JTAGは,もともとチップの回路テスト用に開発されたバウンダリ・スキャンのテスト手法である.JTAGの回路と外部テスト・ピンを利用し,デバッグ回路を追加することによりシステムのデバッグが可能となる.
JTAGを利用したデバッグ機能の拡張は,各社独自の仕様により行われている.こうしたオンチップ・デバッグ機能には,NECのN-WIRE,MIPS Technologies社のEJTAG(Enhanced JTAG;図6),Motorola社のCOPなどがある.
CPU内部にデバッグ機能を持たせることは,CPUを外部から無理やりエミュレーションする必要もなく,実にスマートなデバッグ環境を構成できる.
京都マイクロコンピュータ社ではPARTNER-ET?の拡張機能として,ROMエミュレータの経路とは別に,JTAG経由でデバッグに必要な制御を行うデバッグ機能をサポートした.これによりユーザROM領域を少しだけ占有した小型モニタ・プログラムすら必要としなくなった.同社はそれ以外にもJTAG専用の小型のインサーキット・デバッガPARTNER-Jも商品化している.同製品はCQ出版からもCQ RISC評価キットとしてターゲット・ボードと同梱された形で発売されている.
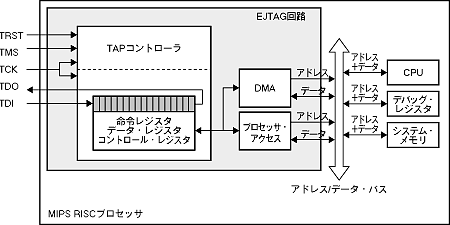
〔図6〕MIPS社のEJTAG(enhanced JTAG)
JTAGを利用したデバッグ機能の拡張は,各社独自の仕様で行っている.EJTAGは,オン・チップ・デバッグ機能の一つである.CPU内部にデバッグ機能を持たせることは,CPUを外部から無理やりエミュレーションをする必要もなく,実にスマートなデバッグ環境を構成できる.


