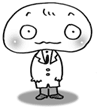今週末、はじめての北海道・東北地区大会が開催される。
昨年2007年の12月に岩手県立大の曽我先生とお会いし、今年の1月には小林さんと岩手県立大を訪問した。そしてこの週末、待ちに待った北海道・東北地区大会が開催される。嬉しい。とっても嬉しい。
組込み教育は主として首都圏で行われており、地方での大々的な教育は稀である。そんな状況下において、自動車関係で大きく盛り上がっている九州と同時期に、盛岡にてETロボコンを開催できることは非常にうれしく思う。
さすがに、他の地区の方々は北海道・東北地区大会を見学するのは難しいかもしれないが、なんと岩手県立大にてインターネット中継が行われる。
http://www.comm.soft.iwate-pu.ac.jp/etrobo.html
どんな大会になるか楽しみである。昨年は、もっとも参加チームが少なかった東海地区が、全国大会やチャンピオンシップにて大活躍をしたことが記憶に新しい。今年の参加チーム数としては、北海道・東北地区大会がもっとも少ない。
近年自動車関係のソフトウェア開発において企業誘致が進む、東北地方と九州地方、この二つの地区大会がどのような結果になるかも気になる。これからの自動車における付加価値を決めるソフトウェア。この2地区がチーム数では小差で九州地区に軍配が上がったが、それぞれの地区大会でどんな記録がでるのか、さらにはチャンピオンシップでの上位進出はどちらが多いのか。北海道・東北地区はそんな争いもあり、目が離せない大会である。
2008年8月アーカイブ
先日はJEITAのセミナに参加してきた。
前代未聞の100人ワークショップのアドバイザとしての参加である。
この前代未聞のワークショップは赤青黄の葉書大の用紙を掲げることで全員参加且つ双方向のコミュニケーションを実現した。さらには同じ机に座る三人の議論も実施してもらい、解決策の選択肢抽出も行った。これにより全員が議論に参加するワークショップを実現した。
このアイデアは素晴らしく、今後のロボコンにおけるワークショップでも利用できるかもしれない。
このセミナでは全員参加のワークショップ前に、基調講演・招待講演、そして2件の事例紹介が行われた。ETロボコン関係で注目すべきは、IPA/SEC:平山さんの招待講演と、松下電器:南光さんの事例紹介である。
SECの平山さんは「組込み分野へのソフトウェアエンジニアリングの活用法」というタイトルでの講演である。モデリングや形式検証などの技術を、どのように導入・活用すべきかを考えさせる内容であった。なかでも私が気に入った表現は、フォーマルでなくセミフォーマルという表現であり、仕様書や設計書を形式手法で表現するのではなく、目次や書くべき内容を組織で標準化し、設計効率やレビュー効率を高め、生産性や品質の向上に貢献するというもの。(正確な表現でないので、詳細は後々公開されるであろう平山さんの講演資料を参照願う)
松下電器の南光さんは「モデル駆動型開発の導入による生産性向上の事例」として、MDDの導入背景、導入手順や効果・課題などを報告してくれた。松下電器のような大手企業だからできるのだ!!と言われそうな事例であるが、やはり推進者の想いとスキルが重要であると思う。生産性などの向上は数値的に語られていたが、そこばかり気になる人も多いかもしれない。しかし本質は、開発スタイルの転換であると感じた。今後、日本のメーカがどのような競争優位を、どのような価値を、どのようなスタイルで提供していくべきかを考えさせる事例である。開発現場では製品のライフサイクル短縮化、開発期間の短縮化、グローバルな市場と開発体制などが押し迫っている。そんな中、我々エンジニアはどのようなスタイルで開発を行うかを考えるべきでいい事例だった。
いよいよETロボコン地区大会、すでに7月に開催済みの東海地区以外の4地区大会が始まる。4週連続という怒涛の大会開催ラッシュである。参加チームのメンバは準備に忙しいだろう。地区および本部の実行委員会も大忙しである。
この忙しさが我々のスキルとなり、モデリングが必須となる開発スタイルにおいて活躍できるエンジニアが増えてほしい。その時には、大活躍しているエンジニアが、ETロボコンで学んだと言ってくれていれば、我々実行委員会としてこの忙しさが報われるのかもしれない。
![]() 本日、関西地区試走会が開催されている。いい感じ。
本日、関西地区試走会が開催されている。いい感じ。
本番会場と同じ会場で行われる試走会である。これは関西地区の特徴ともいえる。
昨夜は試走会の準備が順調に進み、予定よりも早く終わった。
参加経験を持つ実行委員が多いことがこのような時にいい結果を招く。
なので、関西地区実行委員長である江見先生お勧めの"妖怪電車"に行ってきた。
これはこのBlogとは直接関係ないが、ある意味、日本全国でロボコンを開催していることのご褒美的なものだと認識している。準備がしっかりしていないと、このような観光は不可能であるから。 この妖怪電車、路面電車の京福電鉄が京都の妖怪祭りに合わせて運行する電車であり、一日数本運行している。車内は薄暗く、妖怪が一緒に乗車する。小さい子供は泣いてしまっている。この鳴き声がより妖怪電車を盛り上げる。
この妖怪電車、路面電車の京福電鉄が京都の妖怪祭りに合わせて運行する電車であり、一日数本運行している。車内は薄暗く、妖怪が一緒に乗車する。小さい子供は泣いてしまっている。この鳴き声がより妖怪電車を盛り上げる。
非常にチープな感じだが、乗客は大喜び。太秦のエンターテイメント性を感じる。
お化け屋敷のようなハードウェア的なアトラクションでなく、電気の色や音響、そして妖怪の巡回といったソフトウェア的なアプローチで人々を楽しませている。
ETロボコンもソフトウェアで勝負する。妖怪電車もアイディアをハードウェアでなく、ソフトウェア(これをサービスというのだろう)で盛り上げる。無理やり繋げた感は否めないが、京都の夜にソフトウェアの重要性を感じてしまった。
関西の試走会自体は、まったりとした感じで始まっている。会場もシンポジウムをやるようないいホールである。今年のETロボコン地区大会として最後に開催される関西地区大会。他地区の結果を見てプレッシャーも高まってしまうかもしれない。けど、関西人特有のユーモアをもったエンターテイメントで、おもろい大会になってくれればと願う。
昨日は名古屋。今日は京都。
今週は金沢も行って来たので、飛び回っていると実感。全国各地を飛び回るエリートビジネスマンとは違うけど、仕事もボランティアも楽しんでいるのでオッケーかと。
 来週はリフレッシュ休暇で長期休暇となっている。けど家族サービスは火曜日と木曜日しか出来なそう。火曜日と木曜日は夏休み気分を子ども達と楽しみたい。
来週はリフレッシュ休暇で長期休暇となっている。けど家族サービスは火曜日と木曜日しか出来なそう。火曜日と木曜日は夏休み気分を子ども達と楽しみたい。
夏休みの観光地である京都に一人来ている。周りは観光客ばかり。国際的な観光地なので外国人も多い。
地区大会の最後である関西地区大会も試走会開催を迎える。
関西地区の実行委員会メンバとはET-West以来久しぶりである。また陽気な面々に会えることは嬉しい。
 今日は昨日の名古屋と違い得意な肉体労働。ダイエットだと思って頑張りたい。しかし、最近の全国行脚で少しバテぎみなので無理はしないと自分に言い聞かせる。
今日は昨日の名古屋と違い得意な肉体労働。ダイエットだと思って頑張りたい。しかし、最近の全国行脚で少しバテぎみなので無理はしないと自分に言い聞かせる。
ちなみにテストコースや電池配布など、試走以外にも稼働はかかるものです。
先日、8/31に開催を控えたWROJAPAN本選大会の広報&運営会議を開催した。
プレスリリースや当日のスクリーンや音楽、受付・誘導などを調整した。
この会議の開催は翌日以降で日程調整をしていたが私を含め参加者の業務都合で開催は急遽、翌日の20:30からの開催となった。
私は業務で金沢に出張しており、小松空港18:00頃のフライトで東京に戻り、会議に参加した。
 今回の金沢は観光する時間が無かったが、緑が多く気持ちいい風が吹き抜ける観光地の金沢から、一気に日本橋へと移動した。夜の日本橋もライトアップされ、記念撮影している人を観て、ここも観光地であることを思い出した。
今回の金沢は観光する時間が無かったが、緑が多く気持ちいい風が吹き抜ける観光地の金沢から、一気に日本橋へと移動した。夜の日本橋もライトアップされ、記念撮影している人を観て、ここも観光地であることを思い出した。
本選大会も観光地である横浜である。私も含め歴史ある横浜にて開催される大会を楽しんで欲しい。気持ちいい潮風を感じることができる横浜を。
写真を整理していたら東海地区大会の懇親会の写真が数枚でてきた。みんないい笑顔をした雰囲気のよさが蘇った。
いい結果を出せたチーム、逆に失敗してしまったチームが入り交じった懇親会である。
しかし、みんないい笑顔。これはETロボコンの隠れた効能だと気づいた。
モデリングとプログラム、そして調整・キャリブレーションとの格闘から解放されるのだから、笑顔量もマックス値を示すだろう。
同じ課題に対して、同じハードウェア制約下で取り組んできた競争相手、もしくは戦友とのインフォーマルな交流ができる場である。
ぶっちゃけ話、ロボコン以外の仕事の話、以外なところに共通の知人がいたりといろいろな話が聴けるので楽しい。
ライバルや戦友との語らいを提供する懇親会は、モデリング教育に負けないくらいロボコンのマストイベントである。これは私の思いでなく、実行委員長をはじめ実行委員会の総意である。
昨年の関東地区大会では懇親会会場に当日のビデオが流され、いい酒のツマミになっていたことを思い出した。あの時、うるさかったメンバは今年もロボコンに関与してくれている。チームメンバというよりは、若手の参加を支援してくれていることを聞くと、とても嬉しく思う。
この月末から東北、九州、関東、関西と地区大会が毎週末に開催される。そしてもちろん懇親会も。どんな人とどんな話ができるのか今から楽しみである。またたくさんの笑顔に逢える。
8/2に福岡のシステムLSIセンタにて、ETロボコン九州地区大会の第1回試走会が開催された。 九州では初めての大会開催であり、ETロボコン参加経験者が少ないことから、本部から二上さんと私が派遣された。前日の金曜日の夕方から準備を始め、想定外のこともあったが無事に準備を終えた。
九州では初めての大会開催であり、ETロボコン参加経験者が少ないことから、本部から二上さんと私が派遣された。前日の金曜日の夕方から準備を始め、想定外のこともあったが無事に準備を終えた。
この金曜日には福岡市内で花火大会が開催されており、地下鉄や夜のお店には浴衣の女性が多く、いい雰囲気であった。おっと余談でした。
試走会当日もすんげぇー熱い日であった。朝からジリジリと蝉がうるさく鳴き散らし、日差しはジリジリと半袖の腕を焼いていく。
試走会は九州実行委員長の福田先生のあいさつから始まった。これまで試走会で実行委員長が挨拶をしたことはあっただろうか。アットフォームな雰囲気ながら、産学官がキチンと連携しているのが九州の特徴といえる。仲間になりたいと思わせる雰囲気があるんだな。 午前の試走会と並行して、九州の実行委員会を開催。特にモデル審査やワークショップについてイメージ合わせを実施した。これも経験者が少ないことが原因で、心配な事項が多々あるとのこと。本部としては完璧なパッケージとしてモノや情報、審査員などを提供できればと思うのだが・・・。写真は九州地区の審査委員4名による打合せ風景。
午前の試走会と並行して、九州の実行委員会を開催。特にモデル審査やワークショップについてイメージ合わせを実施した。これも経験者が少ないことが原因で、心配な事項が多々あるとのこと。本部としては完璧なパッケージとしてモノや情報、審査員などを提供できればと思うのだが・・・。写真は九州地区の審査委員4名による打合せ風景。
私は夜に東京(正確には千葉県市川市)にて私用があったので、昼過ぎに試走会場を後にした。午後からは私の所属する会社のチームが試走であり、もう少し見ていたかったのだが、後ろ髪を引かれながら福岡空港へ向かった。しかし、私の会社のチームは、いい走りをしていたようである。当日の調整やモデルで失敗しないでほしいと願う。
九州大会は今週末に第二回の試走会を実施予定。そして、9/7(日)に本番を迎える。特に福岡市のチームに注目が集まるが、自動車産業の誘致や活性化にかける九州としてはいいタイムやいいモデルがどれだけ出せるか楽しみである。
これまた時間がたってしまったが、8/7に福岡の麻生情報ビジネス専門学校で開催されたWRO Japan九州・山口地区大会に審査員として参加してきた。 同行した小林さんの総評コメントに感銘を受けた。WRO横浜組織委員会の名誉顧問である有馬先生の言葉を引用しながらのコメントである。このような取り組みは続けなさい。続けることが重要であると。
同行した小林さんの総評コメントに感銘を受けた。WRO横浜組織委員会の名誉顧問である有馬先生の言葉を引用しながらのコメントである。このような取り組みは続けなさい。続けることが重要であると。
やはり今回の上位入賞チームは、これまでも続けて参加し、生徒・先生ともにノウハウを蓄積し、学校という組織としてのスキルを持っていた。一人の優秀な生徒による一過的なスキルとは違った。 最近、開発現場向けに技術継承の話をする機会が増えたが、この話はレベルの違いなどあるが同じと感じた瞬間である。特に学校のように生徒が入れ替わるような環境では先生の意味は大きい。開発現場ではある程度、メンバの流動性は低いのであれば問題はないかもしれない。
最近、開発現場向けに技術継承の話をする機会が増えたが、この話はレベルの違いなどあるが同じと感じた瞬間である。特に学校のように生徒が入れ替わるような環境では先生の意味は大きい。開発現場ではある程度、メンバの流動性は低いのであれば問題はないかもしれない。
しかし近年の開発サイクルの短縮、アウトソーシング多用といった環境では学校と同じように指導者が重要となる。ここでいう指導者は、マネージャーや経営者である。現場レベルでは技術のリードができる人材である。
暗黙知、形式知といった知識を文化と共に継承する必要があり、これは日常としての発言、行動が一貫してないとならない。スポーツにおける反復練習なども意味があると思う。
と、技術の話で語ってきたが、ロボコンの大会運営でも経験を活かし、年々、素晴らしい大会となっている。
麻生情報ビジネス専門学校では3度目の開催であったが、運営のスキル向上を感じた。運営を仕切る生徒は入れ替わっているが、きちんとノウハウが継承されていた。
開発などの技術以外にも、スキルは経験によって成長し、それを組織として継承することは可能であると実感した福岡であった。
これからは、その継承のプロセスを明らかにして、意図的・効率的に、スキルを継承する方法を見つけたい。
ちょっと前になるが、7/31にWRO Japanの教育シンポジウムを開催した。ロボットを使った教育を提供する教員や指導者を対象にしたシンポジウムである。 小中高生のロボットを使った教育に関する情報交換の機会としては珍しい取り組みである。大学の先生方は学会活動などがあるので、情報交換の機会はある。しかし小中高の先生方はこのような機会が稀であるという。
小中高生のロボットを使った教育に関する情報交換の機会としては珍しい取り組みである。大学の先生方は学会活動などがあるので、情報交換の機会はある。しかし小中高の先生方はこのような機会が稀であるという。
今回WRO Japanでは世界大会に先立ち、国内において小中高生を対象にロボットを使った人材育成に取り組んでいる方にお集まりいただきシンポジウムを開催した。
初めての取り組みでありこじんまりとしたシンポジウムを想定していたが、予想以上に多くの方々に参加いただいた。
メディアによる取材があったのも特筆すべき事項である。
このシンポジウムに関する件ではないが最新号の日経ビジネスの特集にWROが登場している。特集は工学部離れに関するものである。
今回のシンポジウムの注目も、やはりこのような背景があると考える。
工学部離れを嘆いたり、危惧するたけでなく、具体的な行動にでる企業や自治体がある。我々はWROという取り組みを通じ、この危機に立ち向かう。
数年後、この教育シンポジウムがもっと拡大し、これにより指導する先生方が増え、そしてものづくりを目指す子ども達が増えればと思う。これは人数だけでなく、いいモノを作った後の笑顔量でも図りたい。
そのためにも、先生方々や、子ども達にいい大会を提供しないとならない。
日本代表を決める日本大会は、今月末に迫ってきた。各地区代表の子ども達も頑張っていると思うので、おじさんももう少し頑張ろう。