携帯機器間のデータ転送を簡単かつ高速に ――既存USBの課題を克服するための追加規格
●USBによって解決されるのか?
上記の条件を備えるデータ転送手段の一つとしてUSBが挙げられます.USBは,すでに広く普及しています.マウスやキーボードのような簡単な機能のものから,プリンタやMP3プレーヤのような複雑な機能を持つ機器まで,パソコン周辺機器のインターフェースとしてよく使われています.3~4年前からUSBは世の中のパソコンのほとんどに装備されています.USB対応製品は,パソコンや周辺機器を合わせて10億台以上がすでに市場に出まわっています.USBは低価格で,じょうぶで,使いやすいという利点があります.1.5M~480Mbpsのモードを備えており,データ転送速度も十分速いと言えます.
しかし残念ながら,利点ばかりではありません.USBにはホスト(一般的にはパソコン)が必ず必要となります.周辺機器どうしのデータ転送であっても,必ず間にホストを通さなければなりません(図1).
ならば,「周辺機器にもホストの機能を持たせればいい」という意見が出てくるのでしょうが,そう簡単にはいきません.USBはいわゆるマスタ/スレーブのプロトコルであり,1台のホストと複数の周辺機器をつなげるための規格です.そういうわけで,転送を左右する「頭脳」の処理は,ほとんどホスト側に集中しています.
USB規格に完全に準拠したホストの「頭脳」を組み込むことは,比較的簡単な機能しか備えていない携帯機器にとっては負担が大きすぎます.
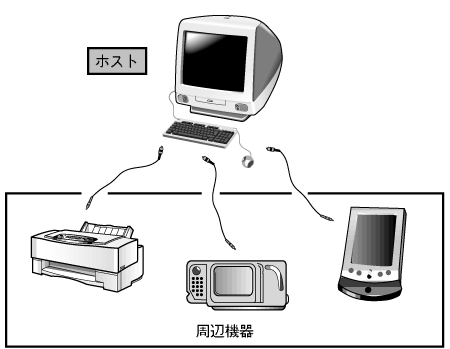
〔図1〕標準的なUSBのバス構成
従来の標準的なUSBのバス構成では,パソコンがホストであり,ほかの機器はすべて周辺機器となる.すべてのデータはホストを通過する.例えば,ディジタル・カメラからの写真を印刷するには,最初に写真データをホストに転送し,その後ホストからプリンタへ印刷するという手順が必要である.周辺機器を直接ほかの周辺機器につなげることはできない.


