携帯型機器向け電源ICの低消費電力技術 ――携帯型機器とともに歩むLDO電圧レギュレータ技術の軌跡
● 低電圧化に伴い,DC-DCとLDOの2段構成に
上記のECOモードの開発とほぼ並行して筆者らが進めてきたのが,低入力電圧を受け入れられるLDOの開発です.
かつて,メイン・デバイスの動作電圧が3V系であったころは,図5(a)のように機器の内部にある5Vライン,または電池(Liイオン2次電池の1セルなど)から,電源IC(LDO)を介して電源が供給される回路構成が一般的でした.これは,LDOの自己消費電流をほとんど無視できると仮定した場合(自己消費電流が負荷電流に対して十分に小さい),5Vラインからでも60%前後の効率を確保できたためです.また,Li 1次電池の1セルからであれば,80%程度の効率を確保できます(電池の平均電圧を3.6V程度とした場合).
しかし,メイン・デバイスの動作が高速になり,高集積化が進むにつれて,製造プロセスの微細化が進みました.これに伴って,メイン・デバイスの動作電圧は1.8Vから1.5V,1.25Vへと低下してきており,今後さらに1.1V以下になるところまで低電圧化が進行しています.
ここまでメイン・デバイスの動作電圧が低下してくると,今までのように主電源(5Vラインや電池)から,LDOで直接電源電圧を作って供給するという方式では,高効率を維持できなくなります.このため,低消費電力設計を目標とした場合,図5(a)の回路構成をまったく受け入れられないケースがでてきました.
代わりに,ここ数年,よく採用されているのが,図5(b)のような回路構成です.まずは,高効率を実現できる降圧のDC-DCコンバータ(スイッチング・レギュレータ)でいったんある電圧に落とし,続いてその電圧からLDOでメイン・デバイスの動作電圧を作ります.
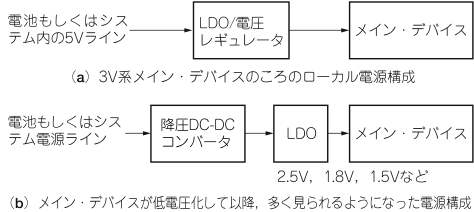
図5 電源構成のトレンド
メイン・デバイスの電源が3V系だったころは,ある程度の効率を確保でき,安価で簡単な(a)の構成が好まれた.その後,低電圧化が進み,高効率を実現する必要性から,(b)のような降圧DC-DCコンバータ(1.8V,1.5V,1.25V)とLDOの2段構成が利用されるようになった.


