アーキテクチャの視点でみたARMコアの変遷と動向 ――LSI設計者は「ファミリ」に,ソフト開発者は「アーキテクチャ」に注目
ARMプロセッサは歴史を積み重ねてきたRISC CPUだが,組み込み機器の中でのみ使われてきたこともあり,そのシリーズ展開は意外と知られていない.ここでは「ファミリ」と「アーキテクチャ」の観点で,ARMコアの変遷と動向について解説する.最新のCortexファミリの概要にも触れる. (編集部)
すでに32ビット組み込みプロセッサ市場の王者となって久しいARMプロセッサですが,この先のさらなる発展のためか,現在はどうも転換のステージに入っているように見えます.そして新たな展開の尖兵となるのが,V7アーキテクチャ,および「Cortex」というネーミングのもと,「A」,「R」,「M」の3文字を冠した新ファミリです.
とはいえ,現在は,ARM7ファミリとARM9ファミリがその応用の広さでも数量でも圧倒的です.従来からの変遷をここで一度整理しておくことは,ARMプロセッサの理解には必須でしょう.なぜならARMプロセッサは非常に互換性を重んじて進化してきています.応用ごとの組み込み開発と割り切ってしまい,互換性など無視して最適化を図るようなプロセッサ開発手法が最近では注目を集めている中で,これまでのARMのポリシは非常に伝統的なものでした(図1).
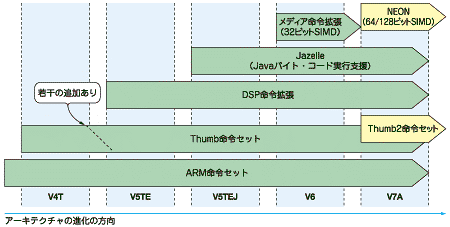
図1 ARMアーキテクチャの主要命令セットの変遷
バージョンが上がるにつれて,命令セットが互換性を保って拡張されていることがわかる.


