つながるワイヤレス通信機器の開発手法(8) ――アーキテクチャ設計を行う
図4に携帯電話に必要な機能と使用されるCPUの規模を示す.機能が多くなるにつれて,CPUの性能は8ビットCISC,16ビットCISC,32ビットRISCと上がっていることがわかる.第2.5世代/第3世代では,通信制御用のCPU(C-CPU;communication-CPU)とアプリケーション処理用のCPU(A-CPU;application-CPU)の二つがメインCPUとして携帯電話に搭載される傾向にある.また,CPUパワーが増えるたびに部品点数が一時的に減少することもわかる.これはCPUパワーに余裕ができるため,それまで外付けのLSI(論理回路)で行ってきた処理をソフトウェア化してプログラムに取り込めるようになるからである.
●8ビットから16ビットへ
第1世代(1G:アナログ方式)から第2世代(2G:ディジタル方式)に移行した際,変調方式や音声のCODEC,および通信プロトコルの高度化によりCPUは8ビットから16ビットに変わった.2Gでは,これらの通信に関連する部分のみではなく,徐々にアプリケーション側の処理(例えばかな漢字変換,メール機能)も増えていった.2Gの携帯電話の時代は数年続くが,その間に通信にかかわる部分はあまり変わらず,アプリケーションの処理が増えていった(例えば,最初は単漢字変換しかできなかった漢字入力が連文節変換できるようになるなど).
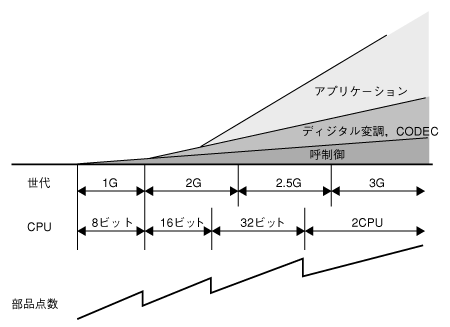
〔図4〕携帯電話に必要な機能と使用されるCPU規模
機能が多くなるにつれて,CPUの性能は上がっている.第2.5世代/第3世代では,通信制御用とアプリケーション処理用の二つがメインCPUとして携帯電話に搭載される傾向にある.


