つながるワイヤレス通信機器の開発手法(8) ――アーキテクチャ設計を行う
また,前者のようにすべての処理を一つのプロセッサで実行する場合,32ビットRISCプロセッサなどが採用されている.例として,一つのARMコアでHCIの上下の処理を行う場合のブロック・ダイヤグラムを図3に示す.図3は,ARMコアを使ったSOC(system on a chip)の典型的な例である.すなわち,メモリなどの高速アクセスを必要とする「AHB(Advanced High-performance Bus)」と,速度を求められない周辺回路向けの「APB(Advanced Peripheral Bus)」の2種類のバスを1チップ上に実装するSOCとなっている.Bluetoothのベースバンドは速度を求められないので,APBに接続されている.
また,32ビットRISCプロセッサを使う場合,Bluetoothの通信に関連する処理だけでなくアプリケーションの処理も行えるように,APIをアプリケーション開発者のために開示しているメーカもある.図3のようなSOCは,ARMコアをベースとした一種のプラットホームといえる.
ARMの場合,上述したようにAPBやAHB以外にも図3のAHB-APBブリッジ,そして,GPIO(汎用入出力),PCMインターフェース,シリアル・インターフェースなど,通常SOCを構成する場合に必要となる周辺機能のコアをライブラリ(製品名は「PrimeCell」)で用意している.そのため,ユーザはPrimeCellにない必要な部分だけを設計し,実装すればよい.図3の場合,Bluetoothのベースバンド,PCM(pulse code modulation)-CVSD(Continuous Variable Slope Delta Modulation)のコアはユーザが設計する.
図3のSOCは一つのプラットホームであると説明したが,例えば沖電気工業の場合は「μPLAT」という商標名でARMプロセッサをコアとしたプラットホーム・シリーズを展開しており,Bluetooth用のベースバンド・チップもμPLAT上で構築されている.
最近のワイヤレス機器のプラットホームとしてはARMが非常に多く,デバッガやソフトウェアなどもたくさん用意されている.また,ARMコアをプラットホームの中核として製品化しているメーカも非常に多い.国内メーカでは,先の沖電気工業のほかにセイコーエプソン(S1C3800シリーズ)などが挙げられる.ARMベースのCPUのほかに,日立製作所(SHシリーズ),NEC(V850シリーズ),富士通(FRVシリーズ),セイコーエプソン(S1C33シリーズ)などがある.また,MIPS系のCPUをコアとして製品化しているメーカとして,NEC(VRシリーズ)東芝(Txシリーズ)などがある.
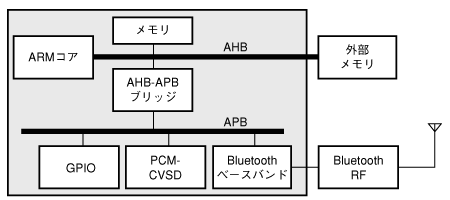
〔図3〕ARMコアでHCIの上下の処理を行う
AHBとAPBは,英国ARM社が開発したSOC設計向けのオンチップ・バス・インターフェースである.Bluetoothベースバンドは速度を求められないので,APBに接続されている.CVSDは,Bluetoothの音声符号化方式の圧縮方式の一つ.


