つながるワイヤレス通信機器の開発手法(2) ――製品機能を決める
●性能と消費電流のバランス
携帯電話,PDAをはじめとする携帯型の機器の場合,ほとんどのものが電池で動作する.携帯機器の場合,電池の重さは機器重量の数十%を占める.携帯機器の魅力である軽さと,1回の充電による使用時間は,つねにトレードオフの関係にある.魅力ある機器にするため,つまり,軽くて使用時間の長い機器にするために,消費電流を少しでも小さくする努力が必要である.
では,消費電流を減らすためにはどのような方法があるのだろうか? 以下に考えられる方法を挙げてみる.
- 微細加工の最新プロセスで製造されたLSIの採用
- 部品の集積化
- 低い動作クロックの採用
LSIの世界では日々その製造プロセスが進歩し,消費電流もそれに伴って低減される方向に進んでいる.最新の設計ルールで製造したLSIに置き換えるだけで,ほかにくふうしなくても消費電流を半分にできたという例は多くある.しかし,このようなLSIは高価である場合が多い.前述のコストとのトレードオフの問題がいつも付きまとうことを覚えておく必要がある.
次に,部品の集積化について説明する.現在の電子回路の大半を占めるディジタル回路は,一定の周波数のクロックで動作する.部品を基板の上に並べて配線した場合,必ず寄生容量が発生する(図3のCi ,Co).一定の周波数のクロックでディジタル回路が動作した場合,この寄生容量に対して充放電を繰り返すことになる.配線の量が増えたり長くなった場合,この寄生容量は大きくなり,充放電のための消費電流も増加する.
部品の集積化を進めれば配線の量が減り,配線長も短くなるので,寄生容量と充放電量が減って,結果として消費電流を小さくすることができる.
また,一般のCMOS LSIの場合,HレベルからLレベルへ,またはLレベルからHレベルへ遷移するとき貫通電流が流れる.これは図3のスイッチAとBが同時にONになる時間があるためである.クロック周波数が上がると,貫通電流が流れる回数が増え,消費電流は大きくなる.よって消費電流を小さくするためには,低いクロック周波数を採用することが有効である.しかし,クロック周波数を下げると製品全体の性能が下がる.消費電流と性能のトレードオフを検討する必要がある.
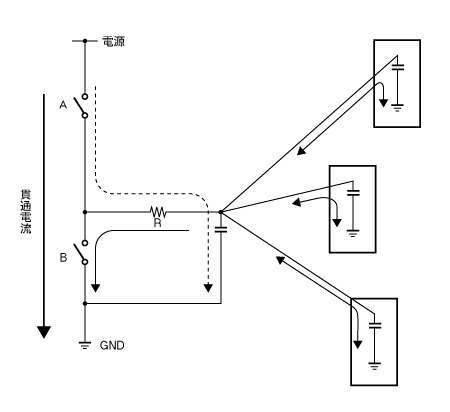
〔図3〕ディジタル回路では寄生容量と貫通電流が問題
図のように部品を基板上に並べて配線すると,必ず寄生容量が発生する.部品の集積化を進めれば,この寄生容量が減少し,消費電力も低減できる.また,スイッチAとBが同時にONになる期間が存在するため,貫通電流が流れ,そのときに消費電流が増える.この対策として,クロック周波数を下げる方法が挙げられるが,機器の性能とのトレードオフになる.


