つながるワイヤレス通信機器の開発手法(2) ――製品機能を決める
通信機器の開発では,通信仕様さえ決まればすべての「製品機能」が決定されると思われがちである.しかし,実際にはコストや消費電流,重量など,多くの項目を考えて,製品に機能を取り入れていく必要がある.今回は,このような「製品機能」の中でも,もっとも重要と思われる項目を取り上げ,その製品機能を実現するための方法を説明する. (編集部)
前回は,仕様の読みかたについて説明した.仕様書を読むと,どのような機器を作ればよいのかを想像できる.
しかし,前回説明した仕様とは通信仕様のことであり,通信仕様だけでは製品はできない.通信仕様とは相互接続性を確保するためだけのものであり,製品としては通信仕様以外にも図1に示すように,ユーザ・インターフェースやコスト,重量など,製品としての機能や性能を表すすべての要素について決める必要がある.ここでは,これらの要素をまとめて「製品機能」と呼ぶ.
通信の世界を外から見た場合,製品機能(仕様)=通信仕様と思われ,誤解を受けることがしばしばある(コラム「通信分野とコンピュータ分野の隔たり」を参照).
図1に示すように,製品を完成させるまでには通信仕様以外にも多くのことを決める必要がある.製品機能は,製品が売れるか売れないかを大きく左右する.ユーザのニーズを反映していなければ,高い費用をかけて開発しても製品は売れないだろう.最悪の場合,世の中に出ることなく,プロジェクトは途中で中止,開発チームは解散ということもあり得る.
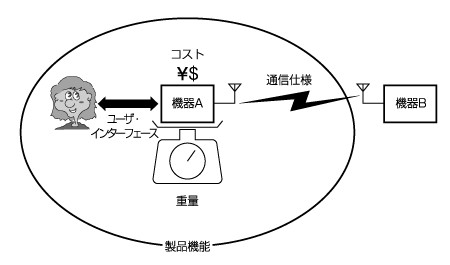
〔図1〕通信仕様イコール製品機能ではない
通信仕様以外に,ユーザ・インターフェースやコスト,重量などといった,いわゆる「製品機能」を決める必要がある.


