Cベース設計教育の カリキュラム構築から運用まで
●三つの部門が連携
「3年間で現在のRTL設計者のすべてにCベース設計をひととおり習得させる」という欲ばった目標を掲げ,それまでツールの開発担当者が行っていた教育をベースに,必要な教材やスタッフなどの教育体制を検討することにしました(それまでのCベース設計についての教育は,ツールの開発メンバが中心となって半年に一度程度入門者向けに行っていた).
まず,社内技術研修所と人材育成部門,EDA整備部門の三つの部門で検討を始めました.EDA整備部門にとっては教育という畑違いの分野で専門家の協力が必要でしたし,人材育成部門にとっては戦略的な人材育成の観点でCベース設計は重要なテーマでした.社内技術研修所は,教育のための設備の貸し出しや教育の運営を行うために参加しました.
目標達成のためには,それまでより1けた以上高い頻度で教育を行う必要がありました.そこで,教育をeラーニング(ここでは,Web上の教材による自己学習)の部分と実習(トレーナによる指導)の部分に分け,よりたくさんの受講生を受け入れてすそ野を広げるとともに,教育内容の深さも追求することにしました(図5).
トレーナについては,現場への適用指導まで行うことを前提に,設計部門の中からスタッフを選び,EDA整備部門が短期集中で育成することにしました.また,このトレーナたちはローテーションを組んで設計部門に戻り,そこでCベース設計のキー・パーソンとして活躍してもらいます(図6).それから,トレーナを取りまとめ,教材開発や教育計画を主体的に進める役割を果
たす「教育リーダ」を設置しました.教育リーダとトレーナはCベース設計の普及という役割上,EDA整備部門に所属することになりました.
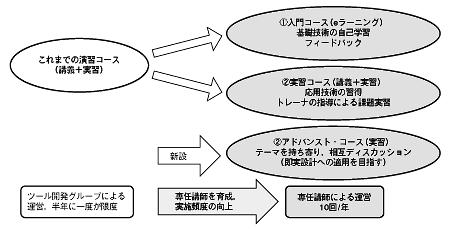
〔図5〕 教育カリキュラムの再構築
すでに,開発メンバによる講義中心の演習コースが存在していた.これをもとに,入門から即適用までの3段階の教育コースを再構築した.現在,入門コース,実習コースまでを立ち上げている.
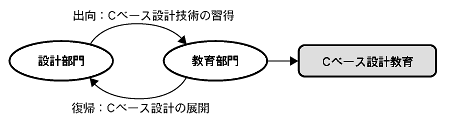
〔図6〕トレーナのローテーション
教育のためにトレーナを抱えるのではなく,トレーナ育成とローテーションを普及の中心にすえる.トレーナは出向元の設計部門に戻り,Cベース設計を根付かせるキー・パーソンになる.


