Cベース設計教育の カリキュラム構築から運用まで
●Verilogな頭をCな頭に!
「RTLによる論理レベル設計から,C言語によるシステム・レベル設計へ」.本教育の目的はこれです(図1).Cベース設計を社内に普及させ,顧客である機器メーカに,他社にまねのできない価値を提供していくのです.ASSP(application specific standard product)ビジネスでは,システム・レベル設計により他社に勝る性能と機能を持つシステムLSIを,他社と比較にならないほどの短納期で提供することを目指します.ASIC(application specific integrated circuit)ビジネスでは,顧客との間で設計データを受け渡すインターフェースの抽象度を引き上げることで,他社と差異化することを目指します.
特に,ASICビジネスについては,システム・レベルまで踏み込んで顧客をサポートできなければ,単なる部品の供給元として買いたたかれてしまいます(図2).装置の付加価値を生み出すための最適なアーキテクチャの提案とそれを実現するためのシステムLSIの提供を行ってこそ,真のシステムLSIビジネスと言えるのだと思います(図3).
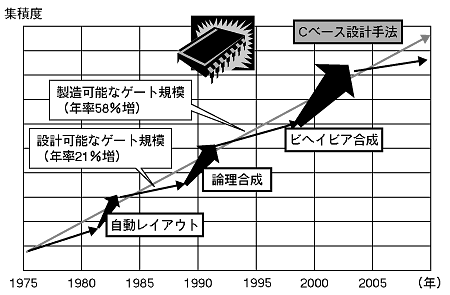
〔図1〕 設計手法の革新
製造可能なゲート規模と設計可能なゲート規模のかい離を何らかの技術革新によって埋めていくという図.1人の人間が設計できるゲート規模を増やすということは,設計する対象を変えるということである.
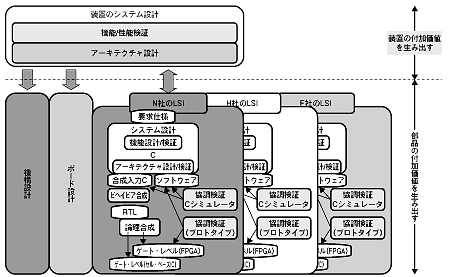
〔図2〕 現在の分担(装置とLSI)
装置の価値は何によって決まるのだろう? 少なくとも,搭載されるLSIの数やLSIの製造プロセス,LSIのゲート数とは無関係である.装置の価値が,機能設計,アーキテクチャ設計という工程で生み出されるとしたら,これより後の工程を受け持つLSIメーカには,付加価値が認められない.買いたたかれるだけ.
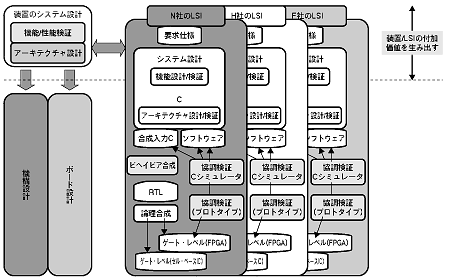
〔図3〕 目標とする分担(装置とLSI)
装置の価値が機能設計やアーキテクチャ設計という工程で生み出されるとして,ここに踏み込んで機器メーカに認められて,初めてシステムLSIビジネスと言える.


