組み込み分野における「マルチプロセッサ」とは ―― 多機能・低消費電力の要求にこたえるための技術的要素と課題
● プロセッサを用いたシステム設計の一長一短
プロセッサはハード・ワイヤード論理と比べて,以下のようなメリットがあります(図1).
- さまざまな機能に対してソフトウェアを再利用することによって,システム全体のハードウェア規模を低減できる(とくに大規模システムにおいて再利用率が高くなる)
- 回路設計後に発見された不ぐあいをソフトウェアで回避・修正できる
- システム設計後に,機能の追加や個人の要望に合わせたカスタマイズが行える しかし,その反面,以下のようなデメリットがあります.
- 回路が冗長になり,単一機能においては性能や消費電力の面でかならずしも最適値ではない
- 開発にあたって,ハードウェアとソフトウェアの両面を設計する必要があり,開発の複雑度が増す
すなわち,プロセッサを用いてシステム設計を行う場合は,次の2点に注意することが重要です.
- 性能や消費電力などを事前に検証することで,必要十分なマージンを明確にしておく
- ハードウェアとソフトウェアの両面を開発,デバッグできるツール群をあらかじめ準備しておく
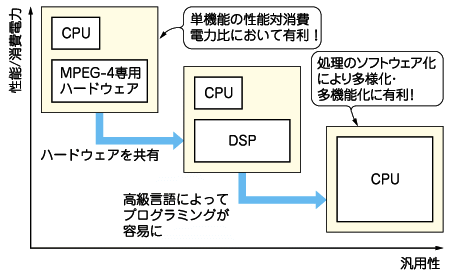
図1 プロセッサのメリット,デメリット
例えば,アプリケーションとしてMPEG-4 CODECを高速CPUですべて処理した場合,DSPを使って処理した場合,MPEG-4専用ハードウェアを用いて処理した場合を考える.一般に,MPEG-4のような信号処理アプリケーションでは,汎用のCPUよりも積和演算器を備えたDSPを使ったほうが同じ処理を少ない消費電力で実行できる.また,MPEG-4専用のハードウェアを作ると,消費電力はさらに少なくなる.これに対して,MPEG-4以外のアプリケーションへの適用を考えると,専用ハードウェアはもっとも汎用性が小さく,CPUがもっとも大きくなる.つまり,汎用性と単体アプリケーションの性能対消費電力比はトレードオフの関係になる.したがって,汎用性を重視するパソコンでは高速CPUが向いているが,機能の限定された組み込み機器では性能が必要な部分を専用ハードウェアやDSPで処理させ,残りを小さなCPUで行うというようなマルチプロセッサ形態が有利になる.


