センサのためのマイコンを選ぶ ──センサ利用のノウハウをファームウェアとして提供
● 使いにくさ,難しさが行く手を阻む
しかし,今までセンサ素子を使ったことのない設計者は,以下のような問題に直面することになります.
- 適切な補正方法がわからない――センサ素子利用のためのノウハウの蓄積がないため,どのように使えばよいのかわからない.例えば,センサ素子が取得したデータはそのままでは使えず,補正をかける必要があるが,どのように補正すればよいのかわからない.
- 多くの周辺部品が必要――センサ素子を使うためには,OPアンプやA-Dコンバータ,コンデンサ,抵抗などの部品が必要になる.これらの部品を外付けするとスペースをとってしまい,小型化が難しい.携帯機器などの市場に投入しにくく,また,一般にコストも高くなってしまう.
センサ素子が必要とする周辺回路の例として,湿度センサを用いて湿度を計測する場合の回路図の例を図2(a)に示します.この図では,OPアンプやダイオードなど,多くの周辺部品を使用しています(1).
筆者らは,これらの課題をローエンドの安価なマイコン(マイクロコントローラ)を使うことによって解決できないかと考えました.具体的には,以下の要件を満たすマイコンが必要です.
- センサ素子に直結できるアナログ・インターフェースを備えていること
- OPアンプ,A-Dコンバータ,コンデンサ,抵抗などに相当する部品を内蔵していること
- センサ素子から取得したデータを補正するファームウェア(計測プログラム)もあわせて提供すること
このようなマイコンを使って課題を解決した場合の回路図の例を図2(b)に示します.ここでは,センサ素子に直結できるインターフェースを持つマイコンと計測ファームウェアを用いて,シンプルな回路で湿度計測を実現しています.
本稿では,温度計測を中心に,4ビット・マイコンを使った計測系の設計について解説します.温度計測はほかの種類のセンサの補正などに利用することも多く,さまざまな場面で応用できます.また,温度計測の応用事例として湿度計測も紹介します.
図2 センサ素子を用いた計測回路の例(湿度センサ)
マイコンを使って外付け部品をなるべく減らすことにより,シンプルな回路で計測を実現できる.
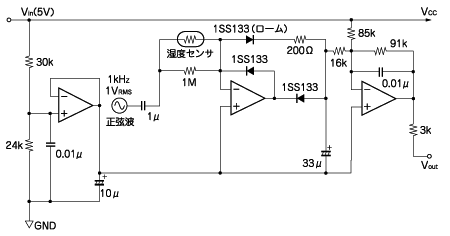
(a)従来の回路
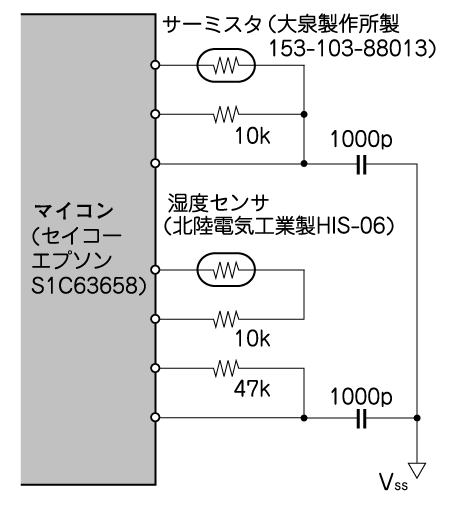
(b)マイコンを使用した回路


