ソフト・マクロのCPUを使おう! ――FPGAによるシステムLSI設計の意味
●マイコン採用時の問題
前述の(1)でいちばん近いと書いたのには深い意味があります.
マイコンは,特定のアプリケーションをねらった仕様になっていることが多いことはすでに説明しました.このため,マイコンが内蔵しているすべての機能を同時に使用できない場合があります.図3のように,マイコンの1本の端子に複数の機能が割り当てられているためです.ある端子をAという機能のために使用すると,その端子に割り付けられているBの機能は使えなくなるのです.パッケージやピン数の制約から,このようなピン割り当てがマイコンでは珍しくありません.アプリケーションが明確であれば,「Aの機能を使うときにはBの機能は不要」という仕様であっても不自由しないかもしれません.使用頻度の高いモジュールは複数の端子に割り付けられていることもありますが,やはり別の機能との選択になります.
最近ではマイコンに内蔵されている機能が豊富になり過ぎているという点も問題になりがちです.
マイコンを希望する形(モード)で動作させるためには,各端子の機能設定を行う初期化プログラムがアプリケーション・プログラム本体の前処理として必須になります.内蔵機能が複雑になればなるほど,初期化プログラムも複雑かつ巨大になります.このため,本来求めている状態まで持っていくためにかなりの時間を要することになります.これには,使わない機能に対して使わないことを指示するプログラムも含まれます.
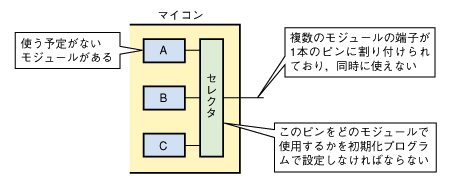
〔図3〕マイコンのI/O部
マイコンの1本のピンに複数の機能が割り当てられていることは珍しくない.1本のピンに割り当てられた複数の機能は,同時に使用できない.また,初期化プログラムが複雑になりがち.


