ソフト・マクロのCPUを使おう! ――FPGAによるシステムLSI設計の意味
●既存の設計資産が生かせない?
―― No! 移行は容易,将来ディスコンの心配なし「CPUを変えると,これまでのソフトウェア資産が使えなくなる」.CPU選択時に限らず,OSや開発環境の選択時にも必ず出てくる話です.しかし,昔のようにアセンブリ言語でプログラミングしていた時代ならともかく,C言語に代表される高級言語でアプリケーション・プログラムを開発している現代では,ほとんどあてはまらなくなったと筆者は考えます(図11).
ソフトウェアの設計資産のことを考えるのであれば,ソフトウェア開発環境についても考えるべきです.開発用ソフトウェアには頻繁なバージョンアップがあります.また数年に1回は,OSのバージョンアップもありますし,パソコンそのものが入れ替わることもあります.プログラムの中には,ソフトウェア開発環境に依存した記述が少なからず含まれるものです.バージョンアップで開発環境に依存する部分の記述仕様が変わったり,新しいパソコン環境へ移行しようとすると,予想以上に多くの工数を必要とすることがあります.このことを考えれば,C言語で記述されたソース・コードを別の開発環境に移行することは,特別なことでもなんでもありません.
設計終了後の保守についても忘れてはなりません.あるとき採用したマイコンがディスコン(製造中止)になってしまえば,後継マイコンへの移植作業が必要になります.どんなに設計資産にこだわっても,けっきょく数年に1回は何らかの形でソフトウェアの移植作業が発生してしまうというのが普通のようです.
ところがソフト・マクロのCPUは,実装するFPGAデバイスが変わってもCPUアーキテクチャはそのまま移行できます.そもそも完全な汎用製品として製造され大量出荷されるFPGAは,ほかのLSI部品と比べるとディスコンの心配は小さいと言えます.かりになくなっても,同等規模のFPGAにリターゲットするだけですみます.こう考えると,設計資産の継続性は,汎用マイコンよりも逆に優位に立っていると筆者は考えます.製品寿命が5~10年と長い産業用機器の開発に積極的にソフト・マクロのCPUが採用されているのはこのような理由からです.
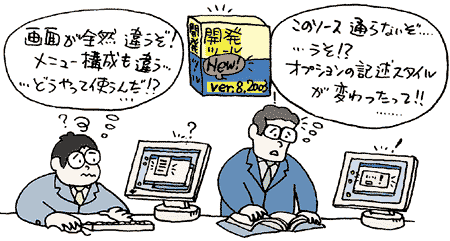
〔図11〕開発ツールがバージョンアップするだけでも...
参考・引用*文献
(1) 浅井剛,「CPU/DSP混載FPGAの設計応用」,第9回 FPGA/PLD Design Conference,2002年1月.
(2) 浅井剛,「最新FPGA/ASICを使い倒す法」,NE/Nμ D Hardware Conference 2002,2002年5月.
あさい・たけし
日立エンジニアリング(株)
●日立エンジニアリング 「PLD Total Solution」のサイト
http://www.hitachi-hec.co.jp/virlsi/pld/pld_top.htm


