つながるワイヤレス通信機器の開発手法(3) ――概要設計を行う
●各段階の評価テストを考慮したV字型設計手法
図8にV字型設計手法を示す.これまでは,どちらかといえば設計主体のフロー(つまり図8の左側)のみが議論されており,図8の右側の流れは軽視されるか(?),設計作業の一部であるかのように考えられてきた.しかし,設計したものは必ず評価テストを行うことと,設計作業は抽象度が高い部分から段階的に詳細な部分に移っていくことを考えれば,設計フローが図8のようなV字型をとることは容易に想像できる.
V字型設計手法をとる場合,各段階で次の項目を決定する必要がある.
- 設計物に対してどのようなテストを行うか
- どのような結果が出たときにOK(テスト・パス)とするか
例えば,Bluetoothモジュールの場合,モジュールとホスト(通常,機器のメインCPU)の間にHCI(Host Controller Interface)というUART準拠のシリアル・インターフェースを持つ.このインターフェースの転送速度の仕様について,以下の三つの考えかたがある.
- Bluetooth Standardに定められた規格
- 内部クロックによって決まる,UARTハードウェアとしての規格
- ソフトウェアも含めたモジュール全体性能としての規格
どのメーカに対してもBluetooth Standardによる規定がいちばん明確である.Bluetooth Standardは以下のようになっている.
ホストとモジュールの間での交渉により,Baud rate(ボーレート)そのほかのパラメータを決定することができる.また,Bluetooth Standardによると,以下の範囲で決定してもかまわない(かなり勝手な規格?).
許容最高速度27.648Mbps~許容最低速度421.88bps
では,上記2)と3)についてはどうだろうか.これはモジュール・メーカのつごうで決まる勝手な仕様である.しかし,モジュール・メーカも,市場調査や顧客の要望を吸い上げて開発しているはずである(たとえそれが売れない機能を持ったモジュールであっても...).
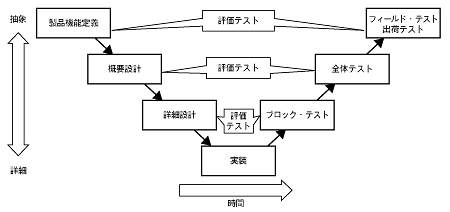
〔図8〕V字型設計手法
設計は,どちらかといえば設計主体のフロー(図の左側)のみが議論されており,図の右側の流れは軽視されるか,設計作業の一部であるかのように考えられてきた.


