つながるワイヤレス通信機器の開発手法(3) ――概要設計を行う
●概要設計のかなめは製品機能の詳細を規定すること
V字型設計手法については理解していただいたと思う.では,具体的にどのように概要設計を行っていけばよいのだろうか.それは製品機能が決まった時点で,その内容を詳細に規定するところから始まる.上記の例のように単にHCIの伝送速度は○○○bpsという形ではなく,
- 動作環境:△△△のテスト環境において
- テスト方法:×××の伝送テストを行った場合
- テスト合格基準:○○○bps以上の伝送速度が出ることというぐあいに,製品機能をより詳細に決めていくことがたいせつである.
くどいようだが,どういったCPUを使ってどのように製品機能を実現するかを決める前に,まず要求される製品機能を詳細に検討して文書化するなり頭の中に叩き込むなりしてほしい.その後,CPUやそのほかのアーキテクチャの選定に入ることが重要である.
重量やビット・レートなどの性能については,机上計算や条件予想などで決めることができる.では,ユーザ・インターフェースについてはどうだろうか(図9).
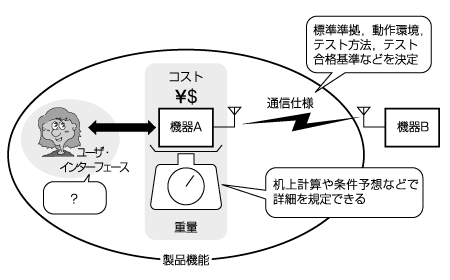
〔図9〕概要設計は製品機能の詳細の規定からスタート
具体的な概要設計は,製品機能が決まった時点で,その内容を詳細に規定するところから始まる.重量やビット・レートなどの性能については,机上計算や条件予想などで決めることができる.では,ユーザ・インターフェースについてはどうだろうか?


