つながるワイヤレス通信機器の開発手法(3) ――概要設計を行う
○● COLUMU ●○
アプリケーションとコミュニケーション
携帯電話の世界では,第1世代,第2世代,第2.5世代にわたり,すべてメインCPUだけ,またはメインCPU+DSPの構成で製品を実現してきた.
しかし,第3世代では二つのメインCPUを使う方向で固まりつつある.この業界では二つのCPUをC-CPU(communication-CPU)とA-CPU(application-CPU)と呼んでいる.第2.5世代までは,通信に関連する高速レスポンスを要求されるタスクを一つのCPUの割り込みルーチンで処理してきた.また,ユーザ・インターフェースのようにどちらかといえば低速のタスクを同じCPUのリアルタイムOSで処理してきた(図A).
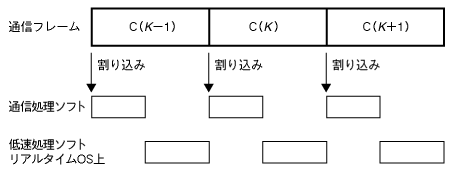
〔図A〕CPU処理
この構成をとると,発信時とハンドオフ時に通信処理ソフトウェアがCPUパワーの大半を占有してしまい,リアルタイムOS上の処理などが止まってしまうことがよくある(携帯電話を使っていて,画面のスクロールがとまってしまう体験をした方は大勢いると思う).
通信処理ソフトウェアは,基地局も含めた無線システムが安定している場合,ほとんど変える必要がない.それに対してアプリケーション側は,かな漢字変換ソフトウェアを新しくしたり,GPS(global positioning system)機能を組み込むなど次々と新しい処理が加わっている.そのためアプリケーション側のソフトウェアはつねに更新されており,そのたびに通信処理ソフトウェアの部分もなんらかの調整が必要になり,ソフトウェア開発工数を増大させてきた.
これらの欠点を克服し,さらに表Aに示すような多くのアプリケーションに対応するため,第3世代からはC-CPUとA-CPUの二つのCPUで携帯電話を実現することになるようだ.
〔表A〕携帯電話のアプリケーション
| 音楽再生 |
| GPS機能 |
| かな漢字変換 |
| 画像付きメール |
| ディジタル・カメラ機能 |
| 大型カラー液晶ディスプレイ |
| 動画再生 |
| インターネット接続 |
| 赤外線インターフェース(IrMC) |
| Java環境 |
また,この動きを受けて,C-CPUについてはNEC,松下電器産業などの日本のメーカが,A-CPUについては米国Texas Instruments社や米国Intel社,日立製作所などが外販に向けて製品を発表している.これらの動きは,より魅力的な携帯電話をより早く顧客に届ける良いしくみになると筆者は思う.パソコンの世界のWintelに若干似ているような気もするが...4).


