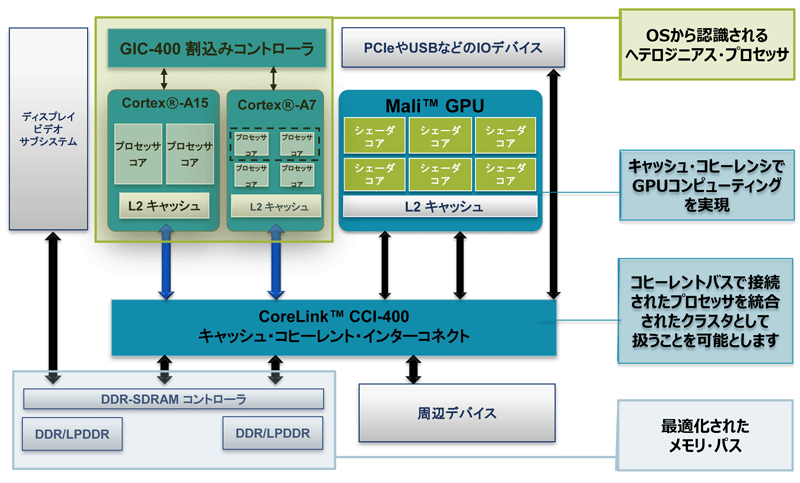重い処理と軽い処理が混在し,電力効率を考慮しなければいけない機器への最適解 ―― 「ETアワード2013」受賞企業インタビュー(7) アーム
一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)は,Embbedded Technlogy 2013(ET2013)で優れたソリューションを提供する企業を表彰する「ETアワード2013」の受賞企業を発表した.ETアワード2013ではあらかじめ予定されていた6部門とは別に,アームの「ARM big.LITTLE」とNECの「低負荷・高圧縮 画像コーデック『StarPixel』」が先端テクノロジー賞に選ばれた.ここでは,アーム 代表取締役社長の内海 弦氏に,big.LITTLEの概要と今後の展開について話を伺った(写真1).
写真1 アーム株式会社 代表取締役社長の内海 弦氏

―― 受賞されたARM big.LITTLEの概要を聞かせてください.
内海氏:「ARM big.LITTLE」とは,重い処理は大きなCPUで処理し,軽い処理は小さなCPUで処理するという,低電力で優れたパフォーマンスを発揮するための概念です.
代表的なところでは,スマートフォンの市場で採用されています.big.LITTLEを発表する前は,2007年にリリースした「ARM Cortex-A9」が2コア,4コアなどの構成でスマートフォンや携帯電話に多く採用されました.しかし,当時のプロセス技術では,Cortex-A9を4コアで使用すると実装面積が大きくなってしまうという課題がありました.
また,Cortex-A9によって電力効率は上がったのですが,実際のスマートフォンの作業として,テキストを打つような軽い処理も,動画像フォーマットのエンコードのような重い処理も同じCPUコアを使用しているという課題も出てきました.
その解決策として,どうCPU処理を配分すればよいかを考案したのがbig.LITTLEです.このように,軽い処理と重い処理が混在する処理のイメージが初めから分かっており,電力効率を考慮しなければいけない機器には,big.LITTLEは最高の処理方法だと思います.
現在は,スマートフォンに採用,検討されていますが,今後は,テレビ,ディジタル・カメラ,プリンタ,車載インフォテインメント・システム(IVI;In Vehicle Infotainment)などにも利用が進むと思われます.すでに,ルネサス エレクトロニクスの次世代ハイエンドの車載情報端末向けSoC「R-Car H2」にCortex-A15とCortex-A7のbig.LITTLEが採用されました.
―― big.LITTLEの具体的な構成は?
内海氏:big.LITTLE対応の原則としては,プロセッサのアーキテクチャが同一であること,かつコアを接続するバス「CoreLink CCI-400」に対応していることが必要となります.現在big.LITTLEに対応しているコアは,ARMv7-Aアーキテクチャ(32ビット)の「Cortex-A7」,「Cortex-A12」,「Cortex-A15」と,ARMv8-Aアーキテクチャ(64ビット)の「Cortex-A53」,「Cortex-A57」となっています.組み合わせは,「Cortex-A7とCortex-A12」,「Cortex-A7とCortex-A15」,「Cortex-A53とCortex-A57」となります(図1).
図1 big.LITTLE SoCのハードウェア構成例
組み合わせは,必ずしもbig.LITTLEに限りません.サーバのように重い処理が必要な機器には「big+big」の組み合わせも可能です.反対に,「LITTLE+LITTLE」で低電力を図る採用事例も出ています,コアの個数の組み合わせも,「big4個+LITTLE4個」,「big2個+LITTLE2個」,「big4個+big4個」,「LITTLE4個+LITTLE4個」や,対称/非対称関係なく「big4個+LITTLE1個」のような組み合わせも,ユーザの意向で可能となります.
―― big.LITTLEを構成する上で必要なライセンスを教えてください.
内海氏:まず,最低限必要なライセンスは,使用されるCPUコアとCoreLink CCI-400です.これらのコアは全て,SystemCベースのモデルを提供していますので,Synopsys社やCadence Design Systems社,Menter Graphics社,Carbon Design Systems社などのESL(Electronic System Level)ツールで,さまざまなbig.LITTLEのシミュレーションを確認することができます.また,それらのモデルとソフトウェア開発ツール「ARM Development Studio 5(DS-5)」をつなげ,仮想(SystemCモデル)のCPUでソフトウェアを開発することも可能となっています.
―― 今後の方向性を教えてください.
内海氏:今後は,車の機能安全に必要な物体認識などに活用が期待されているGPGPU(General Purpose Computation on Graphics Processing Unit;GPUの画像処理能力を画像処理以外の目的にも応用する技術)にも注目しています.そこで,GPUコアのARM Maliは,big.LITTLEの構成にハードウェア的な接続性の最適化を保証しています.今後の展開としては,CPUとGPUの最適化を含めたコンピューティングを提案していきます.
―― 2014年の貴社を取り巻く組み込み市場や環境をどのように予測されていますか?
内海氏:日本の組み込み技術は,自動車,医療,産業機器を見てわかるように,世界的に見ても最先端の技術だとARM社は認識しています.また,日本はトレンド・セッターだと思います.例えば,車の自動運転の要素技術を見ても,ミリ波レーダやセンサ,カメラ,通信など日本の技術が1番進んでいると思います.
2014年は,このような日本のマイコン文化の中に,ARMの明確なポジションを見つけられる年にしたいと考えています.
「ETアワード2013」受賞企業インタビュー 一覧
(1)車載プラットフォーム標準化の流れにキャッチアップしつつ,よりよい仕様を提案
―― 名古屋大学
(2)まず「10mA以下」を絶対目標に定めてLSIを開発 ―― ラピスセミコンダクタ
(3)ワイナリーでは本格的に運用がスタート ―― データテクノロジー
(4)一つの企業だけでものが作れる時代は終わっている ―― ルネサス エレクトロニクス
(5)エナジー・ハーベスティング・ソリューションにmrubyを実装
―― スパンション・イノベイツ
(6)ボタンをピッ! で誰かが牛乳を買ってきてくれる幸せ ―― 村田製作所
(7)重い処理と軽い処理が混在し,電力効率を考慮しなければいけない機器への最適解
―― アーム
(8)探査衛星用に生まれた画像圧縮技術が製造ラインでも活躍 ―― NEC