車載プラットフォーム標準化の流れにキャッチアップしつつ,よりよい仕様を提案 ―― 「ETアワード2013」受賞企業インタビュー(1) 名古屋大学
一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)は,Embbedded Technlogy 2013(ET2013)開催に際して,組み込み業界の発展と国内産業の活性化に寄与すると思われる技術やソリューションを表彰する「ETアワード2013」の受賞者を発表した(写真1).
写真1 ETアワード2013の表彰式のようす

ETアワード2013の「オートモティブ/交通システム部門」では,名古屋大学 大学院情報科学研究科附属 組込みシステム研究センター(NCES)の「TOPPERS/ATK2(Automotive Kernel Version2シリーズ)」およびルネサス エレクトロニクスの「車載情報端末向けSoC『R-Car』シリーズによる統合コクピット向けソリューション」が優秀賞に選ばれた.今回は,TOPPERS/ATK2の開発に携わった名古屋大学 大学院情報科学研究科附属 組込みシステム研究センター(NCES) 研究員の鴫原 一人氏に,受賞したシステムについて話を伺った(写真2).
写真2 名古屋大学 大学院情報科学研究科附属 組込みシステム研究センター 研究員の鴫原 一人氏

――ETアワード2013オートモティブ/交通システム部門部門の優秀賞を受賞した,TOPPERS/ATK2について教えてください.
鴫原氏:TOPPERS/ATK2は,欧州を中心に標準化が進められている車載システム向けソフトウェア・プラットフォーム「AUTOSAR」のOS仕様に基づいて開発したリアルタイムOSです.名古屋大学だけで開発したのではなく,複数の企業とのコンソーシアム型共同研究という形で開発しました.開発した成果物のうちソース・コードと外部仕様書などは,TOPPERSプロジェクトからオープン・ソース・ソフトウェアとして公開しています.
欧州で,車載ソフトウェア・プラットフォームの共通化を目指すコンソーシアム「AUTOSAR(Automotive Open System Architecture)」が組織されたのが,ちょうど10年前(2003年7月)です.同コンソーシアムによってAUTOSAR仕様が策定され,プラットフォームの標準化が進みました.それに伴って,特に欧州では,車載ソフトウェアを車ごとに開発していた状況から再利用型に流れが移ってきました.
日本の現状としては,プラットフォーム共通化よりもできるだけ車の値段を抑えたい,という要求があり,まだAUTOSAR仕様がそれほど普及しているわけではありません.しかし今後,複数のECU(Electronic Control Unit)の機能を一つのECUに統合したり,機能安全対応やソフトウェアのコンポーネント化が要求されたとき,それに適合するシステムを自分たちで一から開発することが果たして可能なのか,そのときは標準化されたプラットフォームを使わざるを得ないのではないか,という懸念があり,自動車関連企業がそれぞれAUTOSARを気にしているという状況です.特にサプライヤ(部品メーカ)などは,発注元から「AUTOSARのバージョンいくつで開発してくれ」と言われたときに,対応できないと困りますから.
そのような流れの中,名古屋大学 大学院情報科学研究科附属 組込みシステム研究センター(NCES)は2011年4月にAUTOSARプラットフォームに関するコンソーシアム型共同研究を開始しました.AUTOSAR仕様は巨大で複雑になっており,またOSのスタック・サイズを決めるパラメータがないなど,欠けている点も多いのが実情です.そのあたりを補いつつ,AUTOSAR OS仕様に基づいたリアルタイムOSの仕様をまとめました(図1).また,サンプルとして提示できるソース・コードを開発しました.
図1 AUTOSARとTOPPERS/ATK2の関係(名古屋大学 大学院情報科学研究科附属 組込みシステム研究センターの資料より)
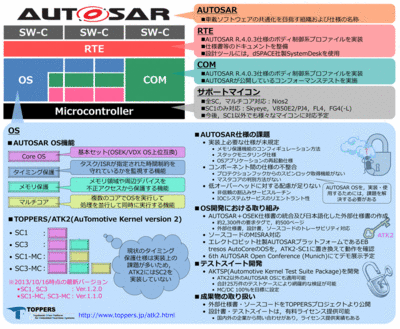
――ツール・ベンダが提供するAUTOSAR仕様のOSと比べて,何が特徴でしょうか.
鴫原氏:まずは,オープン・ソース・ソフトウェアとして無償で公開している点です.無償なので気軽に試せますし,AUTOSARに取り組む際のリファレンスとして使える,という声も聞いています.AUTOSARやOS開発に関する教育にも活用できます.また,TOPPERS/ATK2では,AUTOSAR仕様で足りないと考えた機能,例えばメモリ保護機能などを提案として盛り込み,実装しています.性能面,例えばタスク切り替えにかかる時間なども短縮できるように工夫して実装しています.
逆に,足りない点は,AUTOSARのすべての機能を実装できていないこと,対応マイコンが少ないことなどです.また,サポートを正式に請け負うような体制が取れないので,ツール・ベンダと同じような対応はできません.それでもこのような活動をしているのは,組み込みプラットフォームのOSが全部海外製になってしまうと,日本のものづくり力が低下してしまうのではないか,という危機感があるからです.ツールを買ってきて使うだけになると,中身を知って最適化するということができなくなってしまいますから.
――今後は,どのような活動を予定されているでしょうか.
鴫原氏:現在のコンソーシアムは2013年度で一段落しますが,2014年度から,新たなコンソーシアム型共同研究を開始します.次のコンソーシアムでは参加の敷居を少し下げており,より入りやすくなっています.新たに何社かの自動車会社にも興味を持っていただいています.活動内容としては,機能安全規格対応や時間パーティショニング機能の開発のほか,実装するミドルウェアを増やしていきます.
また,AUTOSAR仕様OSとしてTOPPERS/ATK2の認知度を上げることも重要だと考えています.先日,ドイツでAUTOSARのオープン・カンファレンスがあったのですが,そこでデモ展示を行ったところ,「こういう活動があるということを初めて知った」という日本企業の方もいらっしゃいました.
なお個人的には,「このOSが実際に使われるようになるためには何をしなくてはならないのか?」という問題意識も持っています.単にソース・コードを公開しているだけではだめで,利用したい企業のニーズに沿った活動をできないかと考えています.
――2014年の車載システムはどうなっていくでしょう.
鴫原氏:機能安全がより求められると思います.また,大きなキーワードになるのはセキュリティです.車がネットワーク化し,リモートで制御できるようになってくると,外から勝手にエンジンをかけられたりプログラムを書き換えられるなど,制御を奪われることが大きな問題になります.ただ,物理的にボンネットを開けて入れ替えることまで防ぐべきかなど,どこまでをガードするべきかというのも議論になるでしょう.
「ETアワード2013」受賞企業インタビュー 一覧
(1)車載プラットフォーム標準化の流れにキャッチアップしつつ,よりよい仕様を提案
―― 名古屋大学
(2)まず「10mA以下」を絶対目標に定めてLSIを開発 ―― ラピスセミコンダクタ
(3)ワイナリーでは本格的に運用がスタート ―― データテクノロジー
(4)一つの企業だけでものが作れる時代は終わっている ―― ルネサス エレクトロニクス
(5)エナジー・ハーベスティング・ソリューションにmrubyを実装
―― スパンション・イノベイツ
(6)ボタンをピッ! で誰かが牛乳を買ってきてくれる幸せ ―― 村田製作所
(7)重い処理と軽い処理が混在し,電力効率を考慮しなければいけない機器への最適解
―― アーム
(8)探査衛星用に生まれた画像圧縮技術が製造ラインでも活躍 ―― NEC


