ソフト・マクロのCPUでLinuxを動かす(後編) ──OSの実装とネットワーク対応機器への応用
現在は,組み込み機器向けの32ビットCPUが一般に流通しています.大容量のメモリも安価に購入可能です.比較的小型の組み込みマイコン・ボードでも,OSを動作させるために必要な処理能力とメモリ容量を備えていることが珍しくなくなってきました.例えば最近の機器では,μITRONに代表される組み込み機器向けのコンパクトなリアルタイムOSが採用されています.
従来,組み込み機器でOSを利用する場合,機器の要求仕様に合わせて,デバイス・ドライバやプロトコル・スタック,GUIなどを独自に開発したり,ミドルウェア・ベンダから購入しながら製品開発を進めていました.
最近では製品の開発サイクルが短くなり,より短い期間で高機能なものを開発していかなければなりません.しかし,コストは従来どおりかそれ以下を求められます.従来と同じ開発手法を採っていては,開発工数に見合った人員の確保や品質管理が難しくなります.そこで,設計資産の活用が重要になります.
設計資産の共有という点で注目したいのがLinuxです.これまで自社開発するか,高い費用で購入するしかなかったOSやデバイス・ドライバ,ミドルウェアなどが,オープン・ソースのLinuxを採用することによって,追加コストなしで利用可能になるのです(図2).
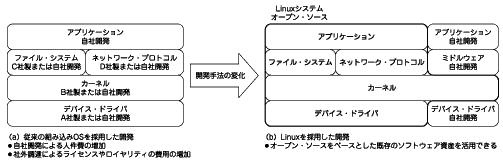
図2 Linux採用によるソフトウェア開発手法の変化
従来の組み込みOSを採用した開発では,自社開発による人件費の増加や社外調達によるライセンス費用などが問題になることがある.Linuxを採用した開発では,オープン・ソースをベースにしたソフトウェア資産を活用できる.


