つながるワイヤレス通信機器の開発手法(11) ──ASICを設計する(中編) エラー訂正回路とタイミング回路の実装
しかし,図7でも示しているが,引き算の演算を行う回路では入力と出力の間でビット幅が1ビット多くなる.つまり,4ビット-4ビットの演算を行うと,その出力は5ビットになる.例えば,-168.75°-168.75°という演算を行う場合,その結果は-337.5(-168.75°の2倍)になる.これを2進数の演算に直すと,
4'b1000+4'b1000=5'b10000
となり,5ビットで表す必要がある.
ここで,図7の遅延検波回路では角度による演算を行っており,演算結果が180°を超えたときは360°からの差分を計算すればよいことになる.先ほどの-168.75°-168.75°の場合は,単純に最上位ビットをけた落としするだけで出力角度を得ることができる.2進数の式に表すと以下のようになる(図8).
4'b1000 + 4'b1000 = 4'b0000
引き算回路に続く位相切り出し回路では,位相から復調データを得る(表3).
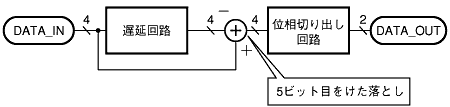
〔図8〕 角度を意識した遅延検波回路
角度演算を意識して図6を書き直した場合.単純に最上位ビットをけた落としするだけで出力角度を得ることができる.
〔表3〕復調データ・テーブル
|
2の補数
|
8を180°とした場合
|
復調 データ
|
|
0110
|
168.75
|
00
|
|
0110
|
146.25
|
|
|
0101
|
123.75
|
|
|
0100
|
101.25
|
|
|
0011
|
78.75
|
01
|
|
0010
|
56.25
|
|
|
0001
|
33.75
|
|
|
0000
|
11.25
|
|
|
1111
|
-11.25
|
11
|
|
1110
|
-33.75
|
|
|
1101
|
-56.25
|
|
|
1100
|
-78.75
|
|
|
1011
|
-101.25
|
10
|
|
1010
|
-123.75
|
|
|
1001
|
-146.25
|
|
|
1000
|
-168.75
|


