実験で学ぶ電池の基礎 ―― モバイル機器を安全に設計するために知っておきたい
電池の中に使われる化学物質には,取り扱いに注意が必要なものがある.電池の正しい使い方を知らなければ,発火や電池の内部から危険な化学薬品が漏れ出すなどの事故を引き起こしてしまう.今回は電池の選定や電子機器を設計するときの基礎知識について,新型電池の研究者が実験などを交えて分かりやすく解説する. (編集部)
1 電池の歴史と分類
● 日本が世界をリードする電池産業
電池というとおなじみの円筒型の単3形乾電池や,携帯電話に入っている角形の電池パックなどを思い浮かべるかもしれません.現在,身の回りで使用される電池には多くの種類があります.秋葉原などで簡単に手に入る単3乾電池を集めてみると,写真1のようになりました.生産量が多いマンガン乾電池やアルカリ乾電池は,世界中に数多くの品種があります.同じ品種の電池であってもメーカごとに特性は異なります.

写真1 市販されている乾電池の例
最近は環境への関心が高まり,使い捨ての乾電池よりも充電できる電池(2次電池)が多く使われるようになってきました.現在市場で入手できる乾電池と同じ形状の2次電池は,ニッケル水素電池と昔からあるニッケル・カドミウム(ニカド)電池です.これらの電池も品種が増えてきました.
特殊な電池としては,災害時に使うマグネシウム電池が市販されています.これは乾電池の形状をしていますが,そのまま使用することはできません.電池に水を注入することで初めて電池として機能します.
電池が発展してきた歴史の中で日本が貢献した役割は大きく,古くは1887年に屋井先蔵氏が乾電池を世界に先駆けて発明したことから始まっています.現在携帯電話からハイブリッド自動車まで幅広く使われているニッケル水素電池やリチウム・イオン電池は,日本の技術で実用化し,世界中に普及しました.高性能な電池の開発では日本が常に世界をリードし,電池は日本を支える重要な先端産業となっています.
研究機関や企業では,より高密度に電気エネルギを安全に蓄える技術や短時間で電気エネルギを電池に蓄える技術などの開発が進められています.図1に示すように電池のエネルギ密度は向上してきており,今後より広い分野での応用も期待されています.
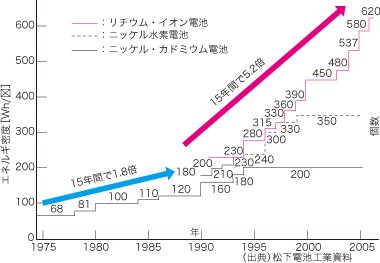
図1 電池の高性能化(1)
携帯用電子機器やハイブリッド自動車の普及にともなって,日本では電池の開発が活発になり,急速に性能が向上した.


