1+1を10にする「チーム力」養成講座 ―― 意見を戦わせより良い成果を生み出そう
4 あるチームの風景
ここでは筆者の職場で実際に行っている,チーム力を向上するための実践例を紹介します(図6).これらは,チームの力を発揮する上で筆者が必要だと感じて経験的に始めたことであり,内容や進め方はチームの進化に合わせて常に変化させています.皆さんの参考になるものがあれば,アレンジして利用していただければ幸いです.
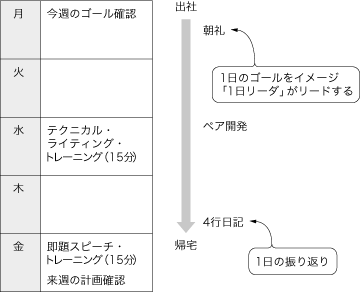
図6 筆者のチームで実践している例
1日の中でやることと,1週間の中でやることをそれぞれ設けている.
● 1日リーダ
その日の開発,特に定常業務がスムーズに行えるように,リードする人を決めます.小学校のころの「日直」のようなものだと考えてください.リーダだけがリードするのではなく,メンバの一人一人がリーダシップを発揮する場を作ります.
● 朝礼
1日リーダが司会を務めながら,メンバの中に,その日を終えたときの仕事や人の状態のイメージを作っていきます.これは,「何をしました」とか「何をします」といったことを報告する場ではありません注1.あくまで1日を終えた時点での成果の状態,誰が何をどのレベルで達成するのかを明確にします.このとき1日リーダは,目標を達成したメンバ自身をイメージするような,リーダ自身の言葉をかけるようにします.「これまで緻密に分析を進めてきたから,結果がOKになればうれしいよね」といった具合です.この達成イメージを持つだけで,その日1日の時間の使い方に随分と差が出てきます.
また,1日リーダが持ち回りで司会を務めることで,自分の仕事だけでなく,ほかのメンバの仕事にも視線を向けることができます.仕事の全体像と自分の仕事との結びつきを感じることによって,チーム感が醸成されます.
注1;ただし,週始めなどは,先週の「頭」を取り戻すために,状況を1分で要約してもらうこともある.
● テクニカル・ライティング・トレーニング
前述の「伝え手が責任をとること」で述べたように,ドキュメントやメールの書き方次第で相手の時間を奪ってしまう可能性があります.そこで,文章の書き方とその効果について考えるトレーニングを行っています(図7).
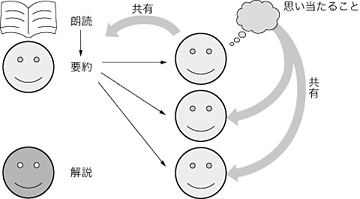
図7 テクニカル・ライティング・トレーニング
1人が参考書の一節を朗読し,要約する.ほかのメンバが思い当たることを話し,メンバ間で共有する.それぞれの役割は持ち回りで担当する.
参考文献(1)をテキストとして進めています.具体的には,まず,その日の朗読担当が文献の一節(1ページ程度)を音読します(朗読).次に,自分が理解したことを自分の言葉でメンバに説明します(要約).そして事例担当が,その日の朗読分に関して,これまでの自分の体験から思い当たることを話し,メンバ間で共有します(事例).最後に,事前に予習しておいた解説担当が,今後の行動に結びつけるようにコメントします.これが通常の流れですが,時には,実際に職場で流れた誤解を招きやすいメール,理解しにくい仕様書,逆に理解しやすい仕様書を題材に,なぜ分かりにくいのか,分かりやすいのかを考える場にしています.
このトレーニングは,週に1度,1回あたり15分,と短時間で進めています.1年も経過すると,参加者たちの書くメールや仕様書に随分と効果が表れてきました.また,分かりやすい書き方について,お互いに意見を出し合えるようになりました.


