1+1を10にする「チーム力」養成講座 ―― 意見を戦わせより良い成果を生み出そう
● その3:伝達する目的を明確にすること
コミュニケーションには目的があります(図3).なぜ相手に情報を伝えるのか.この「なぜ」の深さが浅い段階で情報を発信すると,受け手は困惑します.
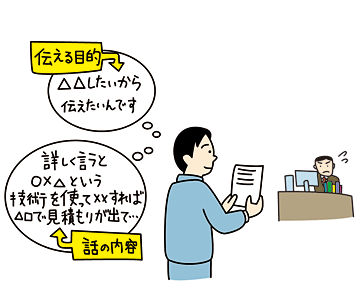
図3 「伝える目的」を伝えることが重要
例えば,あなたが開発リーダに「xxxの新しいアルゴリズムを考えました」と技術的な詳細を延々と報告したとしましょう.リーダは,あなたが新しい案を考え出したことは評価するかもしれません.しかし,その案に関心がなければ話はそこで終わってしまいます.それどころか,忙しくて時間のないときは最後まで聞いてもらえないでしょう.
あなたは,なぜそれを伝えたかったのでしょうか.もし,あなたが「新しいアルゴリズムを評価する時間が欲しい」のであれば,「承認してほしい」というコミュニケーションの目的を伝えなければならないのです.
この例の場合なら,報告の冒頭で「新しいアルゴリズムの評価を承認していただきたいので」と,話の目的を伝えるのです.最初に目的を伝えるだけで,その後に続く技術的な内容をスムーズに伝えることが可能になります.
● その4:事実と意見を区別すること
次の三つの文章の違いを考えてください.
1)それは...です.
2)それは...だと思います.
3)それは...だと考えられます.
普段,これらの言葉の違いを意識せずに使っているとしたら,あなたはチーム・メンバを困惑させたり,誤った情報に振り回されたりしているかもしれません.なぜならば,情報の正確さが異なるからです.1)はより事実である可能性が高く,2)と3)は意見にすぎません.
開発上の課題を解決する道筋を考えるにあたり,起点にする情報を誤ると,ゴールに到達できません.ですから,情報を受け取ったら,まず,それは事実なのか意見なのか,さらに,誰が言っていることなのか,根拠はあるのかなどを確認しましょう.
● その5:理解を確認すること
人が外界から情報を得てから理解するまでの過程は,図4のモデルで考えることができます.チーム開発を進める上で気を付けなければならないのは,すべてのチーム・メンバが同じ復号器を持っているわけではない,ということです.打ち合わせで同じ話を聞いたり,同じドキュメントを見たりしても,理解の程度がおのおののチーム・メンバで異なる可能性があるのです.
ですから,自分が理解したと思っていることを,必ず相手に確認しましょう.何か説明を受けたときには,自分なりに解釈して,それを自分の言葉で相手に説明してみましょう.その説明についてチーム・メンバに聞いてもらい,理解が正しいかを確認します.このサイクルを繰り返すことによって,お互いの理解が近づいていくのです.
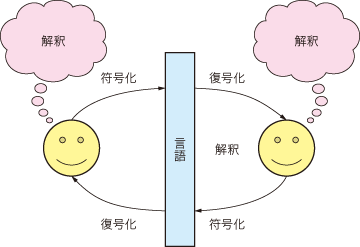
図4 情報の受け取り方や伝え方には個人差がある
情報を伝える際や受け取る際には,その人固有の解釈が入る.


