1+1を10にする「チーム力」養成講座 ―― 意見を戦わせより良い成果を生み出そう
● その5:メンバの不安を取り除く
人は不安があると行動しにくくなるものです.そこで,開発リーダは普段からチーム・メンバが不安を抱えていないかどうか,話を聞いて回ります.そして可能な限り,その不安を取り除くように支援します.
まずは事実の確認から始め,どこに不安を感じているのか明確にしていきます.漠然として言語化できないからこそ不安に感じるものですから,会話を進めながら,一緒に探り当てていきましょう.抱えている不安を聞いてもらえるだけでも随分と楽になるものですが,それを取り除いていく際には,視野を広げて不安を感じている部分を俯瞰(ふかん)したり,見方を変えたりする会話が有効です.
また,人は自分の能力には気付きにくいものなので,リーダがメンバの能力を思い出させてあげることが有効です.「できるかもしれない」と思うと勇気がわいて,次の行動に移れるようになります.その上で,具体的な話を進めると効果的です.
● その6:仕事の意識付け/意味付けを行う
意識付け,意味付けは,チーム・メンバの成長を促進するために行います.仕事を始める前に「意識付け」,仕事を完了した時点で「意味付け」を行います(図5).「意識付け」は,その開発を通して身に付けられる技術と,身に付ける意味について,その技術を身に付けたメンバ自身をイメージできるように会話を進めます.この意識付けを行うことにより,身に付けたい技術が開発を通してより染みこむようになります.「意味付け」は開発の振り返りと同時に行い,開発を通して体験した技術をスキルとして定着させるために行います.
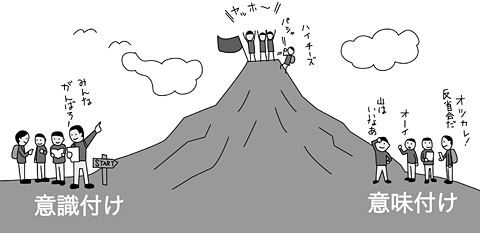
図5 仕事の前に「意識付け」を,仕事の後に「意味付け」を
まず,開発を通してどんな体験をしたのか思い出すように会話を進めます.そして,そこから何を学んだのか,それは今後のチーム・メンバにどのような影響を与えるのかを話し合います.これらを繰り返すうちに,「なんとなくできていたこと」が「きちんと意識してできること」になり,自信を持てるスキルになります.
● その7:リーダ自ら成長する
より大きな目標に取り組めるようにチームを成長させるのは,リーダの役割です.では,リーダはメンバの成長を見守るだけでよいのかというと,決してそうではありません.むしろ,リーダ自身の成長意欲がチーム・メンバに波及し,メンバの成長を促していくのです.
成長意欲のないリーダのチームは,どのような状況に陥るのでしょうか.例えば,ある専門性の高い仕事があり,ある時点でリーダしかできなかったとします.そして,月日がたち,後輩が育って,その仕事を担当するに十分な力を付けるようになったとしましょう.もし,そのような状況になってもなお,リーダが「これは自分しかできない仕事だ」とそこにとどまり,手放さないのであれば,後輩は新しい仕事に挑戦する機会を失います.その結果,玉突き衝突を起こしてチーム全体の成長が止まってしまうのです.
よって,リーダは自ら新しい領域の仕事に挑戦し,リーダの仕事をメンバに任せることにより,チーム全体が伸びていくように環境作りを心がけましょう.


