マルチプロセッサLSIに適したオンチップ・ネットワーク ――ダイレクト・データフロー・インターコネクト
1. バス・インターフェースの問題
マイクロプロセッサのインターフェースというと,バス構造(アドレス,データ,コントロール)をとるのが一般的です.これは,米国Intel社の8080,米国Motorola社(現Freescale Semiconductor社)の6800といった8ビットCPUの時代からあまり変わっていません.これらのバスに直結できる各種周辺LSIがCPUメーカのみならず多くの会社で開発されて流通し,デファクト・スタンダードになっています.
システムLSIにおいても,例えば英国ARM社はAMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)というバスを開発し,公開しています.このAMBAバスに直結するIP(intellectual property)コアは,数多く開発されて流通し,デファクト・スタンダードになっています.ここでもプロセッサ・バス(インターフェース)という概念が踏襲されています.
典型的なシステムLSIの構成を図1に示します.この図で示すオンチップ・ネットワーク部分が,おのおののコンポーネント(プロセッサやメモリ,ハードウェア・モジュールなど)を接続する媒体です.バス構造が一般的ですが,クロスバ・スイッチやメッシュ構造など,複雑なオンチップ・ネットワークを採用したシステムLSIも設計されています.設計エンジニアが独自に開発することもできますが,デファクト・スタンダードのバスをそのまま利用するというケースが多いようです.
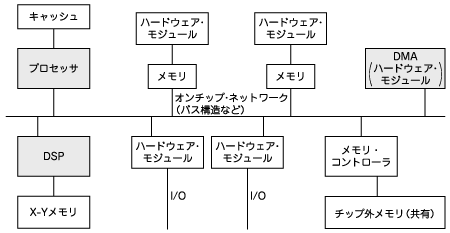
図1 一般的なシステムLSIの構造
オンチップ・ネットワークによってプロセッサやメモリ,ハードウェア・モジュールなどを接続する.バス構造が一般的だが,クロスバ・スイッチやメッシュ構造など,複雑なオンチップ・ネットワークを採用したシステムLSIも設計されている.


