ネットワーク・プロセッサを使ってネットワーク・ボードを開発する ――電源回路設計の留意点とボード実装時のトラブル対策
図5の中にある「リセットIC1」は,検討を行っただけで実際のボードには搭載していないので,リセットICは2個です.1.3V電源回路に用いているICのシャットダウン入力ピンにCRの遅延回路を付けて,3.3Vが立ち上がるまで1.3Vを出力しないようになっています(図6).
このような回路にした理由は,実は適当なリセットICを入手できなかったためです.この回路では,抵抗とコンデンサのばらつきでOE(output enable)信号が解除されるタイミングがまちまちになります.本ボードでは納期の問題があり,最悪値で計算しても1μsを下回ることがない遅延回路を入れることにしました.CRの時定数は,前段にある3.3V電源回路の立ち上がり特性と1.3V電源ICのOEピンのスレッショルド電圧によって変化します.本ボードでは,ほかの部分で使っている部品と共通化するため,C=0.47μF,R=576kΩとしました.
なお,初期のIntel社の評価ボードではこの部分は考慮されておらず,1.3V電圧のほうが先に立ち上がっていました.最新の同社の参考回路図では,リセットICの使用を推奨しています.
リセット回路の設計にあたってもう1点注意しなければならないのが,「PWRON_RESET_Nが"L"の期間には,かならずRESET_IN_Nも"L"にしなければならない」ということです.これは,外部のLSIへの書き込み信号(例えば,EX_WR_N信号など)はPWRON_RESET_Nが"L"でかつRESET_IN_Nが"H"の期間に不定になる可能性があるためです.この期間が存在するため,拡張バスに実装されているフラッシュ・メモリがロック状態になってしまった例があります.原因は,RESET_IN_Nが"H"で,かつEX_WR_Nが不定であったため,フラッシュ・メモリの内部ステート・マシンが不定に遷移してしまったことによるものでした.このような不ぐあいは,回路(ハードウェア)設計時でないと回避しづらい現象なので(ソフトウェアによって回避できない),とくに注意したほうがよい部分と言えます.
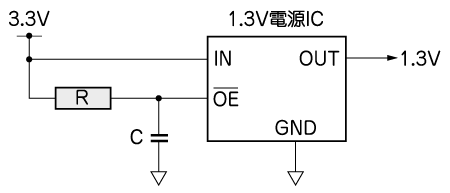
図6 電源ICに遅延回路を付ける
CRの遅延回路を付けることで,3.3Vが立ち上げるまで,1.3Vを出力しないようにしている.


