つながるワイヤレス通信機器の開発手法(10) ──ASICを設計する(前編) 送信側のデータ処理の実装
2ビット分の入力データ(IN_DATA)を1ビット分ずらしてシリアル-パラレル変換(1ビット→2ビット)する(図8).その2ビットの値から,QPSKテーブル回路でIとQのそれぞれ4ビットずつの変調データを生成する.このテーブルは表3をもとに設計されている.テーブルの出力はシンボル・タイミングごとに変化するように最終段のフリップフロップ(FF)でたたく(図9).
QPSK変調回路の設計をひととおり説明したが,テーブルの内容やシンボル・タイミングを変更することで,ほかの変調方式も実現できる.例えば8相QPSKの場合は,シリアル-パラレル変換で1ビット→3ビットのパラレル信号にして,テーブルが八つの位相(0,π/4,π/2,3π/4,-π/4,-π/2,-3π/4,-π)を出力するように作ればよい.もちろん最終段のFFについては,3ビットに1回イネーブルになるシンボル・タイミングを使用する(図10).
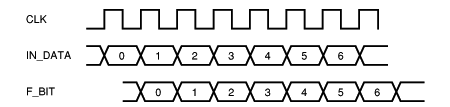
〔図8〕シリアル-パラレル変換
2ビット分の入力データ(IN_DATA)を1ビット分ずらしてシリアル-パラレル変換する.
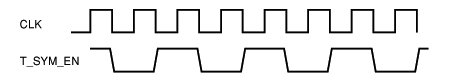
〔図9〕QPSKのシンボル・タイミング
テーブルの出力はシンボル・タイミングごとに変化するように最終段のフリップフロップ(FF)でたたく.
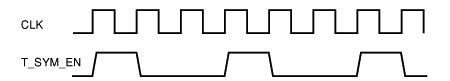
〔図10〕8相PSKのシンボル・タイミング
8相QPSKの場合,最終段のFFは3ビットに1回イネーブルになるシンボル・タイミングを使用する.


