つながるワイヤレス通信機器の開発手法(10) ──ASICを設計する(前編) 送信側のデータ処理の実装
1.送信と受信におけるデータの流れをつかむ
ワイヤレス通信は,所望のデータを送信側から送り,受信側でそのデータを受け取る機能を持つ.図1の中では,この送りたいデータと受け取りたいデータをストリーミング・データとして表している.
送信側では,CPUからレジスタを通して設定されたデータとストリーミング・データをもとに,チャネル・エンコーダで通信仕様に沿ったフレームを組み立てる.その一つの例として,PDC(personal digital cellular)の通話パケット・フレームを図2に示す.図の中の同期ワード(SW)と移動局識別コード(CC)はレジスタで設定する.音声ストリーム・チャネル(TCH)は音声データであり,図1のストリーミング・データに相当する.
チャネル・エンコーダで組み立てられたデータは変調回路に入り,D-Aコンバータでアナログ信号に変換され,RF回路に供給される.RF回路に供給された信号がどのようにして電波に変わっていくかについては,連載第6回で説明しているのでそちらを参照してほしい.
一方,受信側ではまずRF回路から来た信号がA-Dコンバータに入る.A-Dコンバータの出力は復調回路に入り,'1'と'0'のディジタル・データになる.例えば,図2のパケットを受信した場合,受信側はTCH部分のストリーミング・データ出力を得ることができる.また,レジスタを通してSWとCCのデータをCPUで読み取ることができる.
アーキテクチャ設計(連載第8回)で説明したが,無線LAN,Bluetooth,携帯電話のどのシステムに使われるLSIも,図1のようにCPUを内蔵したものが多い.内蔵される主なCPUコアとしては,ARM(沖電気工業のμPLAT,セイコーエプソンのS1C38000など),ルネサステクノロジのSHシリーズ,NECのVRシリーズ,富士通のFRVシリーズ,東芝のTXシリーズなどがある.これらのCPUと周辺回路は,それぞれの半導体メーカが用意するシステム・バスで接続されている.
チャネル・エンコーダの入力,またはチャネル・デコーダの出力であるストリーミング・データは,画像通信であればMPEGなどで圧縮された画像データであり,音声通信であればQCELP(Qualcomm code excited linear prediction)などで圧縮された音声データになる.これらの圧縮や伸張を行う回路(図1の点線のブロック)もベースバンドLSI(またはチップセット)に含める場合がある.
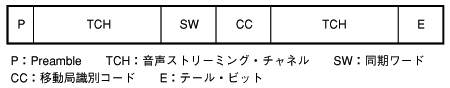
〔図2〕フレーム例
例としてPDCの通話パケット・フレームを示す.


