1トランジスタ構成の疑似SRAMは携帯機器分野で開花するか? ――バッテリ寿命,高集積度への市場要求に対する一つの答え
●バッテリの寿命を延ばすためのリフレッシュ方法
メモリの集積度と処理速度の向上が要求される中で,低電圧への要求も厳しくなってきています.メモリの電源電圧は3.3Vから2.5Vへ,さらには1.8Vへ移行しており,確実に消費電力の低減に貢献しています.
携帯機器は頻繁にアイドル状態となるため,待機時の消費電力の低減はさらに重要です.データを保存するため,疑似SRAMは待機モード時でもリフレッシュする必要があり,そのため待機中も電力を消費します.そこで,疑似SRAMについて,待機時の消費電力を低減するいくつかの方法が提案されています.
1)活性化領域の限定
活性化領域を限定して,メモリの一部分だけにアクセスします.例えば,64Mビットの疑似SRAMを16Mビットや32Mビットのメモリ・ブロックとして機能させることができます.
2)部分アレイ・ リフレッシュ
部分アレイ・リフレッシュでは,疑似SRAMはユーザの設定に従ってメモリの特定部分のみリフレッシュを行います.ただし,このモードで省電力機能が働くためには,ZZピン(パワー・ダウン・モード用の外部入力端子.アクティブ・ロー)が"L"のときのみであることに注意が必要です.ZZピンが"H"レベルになると,疑似SRAMはフル・アドレス・リフレッシュ動作に戻ります(図4).
3)自動温度制御リフレッシュ
DRAMのメモリ・セルの漏れ電流は,温度に非常に敏感です.高温のときほどメモリ・セルは多く電力を消費します.リフレッシュ時に,内蔵オシレータ回路で設定された一定速度ですべてのメモリ・セルの電荷の充電が行われます.数社のメモリ・メーカは,レジスタ経由でこのリフレッシュ回数を+85℃という最悪ケース(この温度では,一般に余分な電力を消費することが多い)に設定しています.このようなデバイスの場合,プロセッサがメモリの温度を検知して適切な温度に設定してやる必要があります.筆者らが開発した「More Battery Life(MoBL)SRAMファミリ」の低電圧疑似SRAM「MoBL3」には温度センサ・チップが組み込まれています.温度を自動的に検出し,それに従ってリフレッシュ回数を調整する機能を備えています.
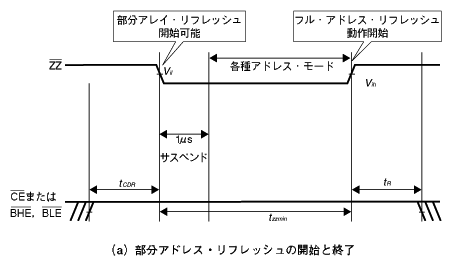
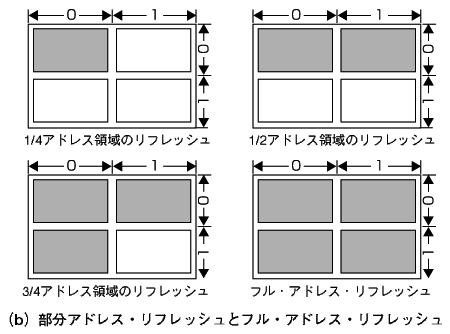
〔図4〕部分アレイ・リフレッシュ
ZZピンの電圧が"L"レベル(Vil)になると,部分アレイ・リフレッシュ・モードの省電力機能が働く.ZZピンが"H"レベル(Vih)以上になると,疑似SRAMはフル・アドレス・リフレッシュ動作に戻る.詳細のタイミングについては,「http://www.cypress.com/support/」で入手できる「Cypress 16M/32M PSRAM」のデータシートを参照のこと.


