つながるワイヤレス通信機器の開発手法(4) ――ハードウェアとソフトウェアを切り分ける
○● COLUMU ●○
ASSPとASIC
本文の中で新規に開発するICをLSIと表現したが,一般的にはASICと呼ばれる場合が多い.ASICと対にして使われることばにASSPというものがある.ASSPとはApplication Specific Standard Products(特定用途向け標準IC)の略で,各半導体メーカのカタログに載っているLSIのことである.
現在,LSIの規模が大きく複雑になってきているため,ASSPを初めから1社または1半導体事業部だけで開発するのは困難になってきている.たいていの場合,半導体事業部と社内の装置事業部または社外の装置メーカが共同でICを作ることになる.その場合,最初にASICとして開発し,装置上で動作確認が終わったものをASSPとして販売することが多い.このようすを図Aに示す.図Aの流れは以下のとおりである.
- LSIメーカの半導体事業部は,A社の装置事業部とASICを共同開発する.その際,仕様書や設計データはA社から出される場合が多い.
- ASICができたところでA社はそれを製品に載せて機能や品質の確認を行う.
- ASICの確認が終わった後,LSIメーカはASSPとして他社(図AではB社,C社,D社)に外販する.この際,LSIメーカはメンテナンスやデリバリについて責任を負う.
上記の説明ではA社のメリットが見えにくいが,量産効果によるLSIの低価格化というメリットがある.また,権利関係(上記の1)で出した仕様書の知的財産権)によっては,売上の一部をロイヤリティとして入手することができる.もちろんA社はLSIメーカと協議のうえ,ASSPとしての外販を数ヵ月から1年程度遅らせることもできる.これらのしくみによってA社の優位性が保たれることになる.
やはり,最初の製品を考え出したメーカがいちばん強いということになる.エンジニアのみなさん,がんばってつねに「いちばん最初」となる製品を開発しましょう.
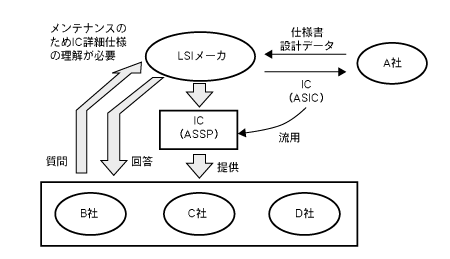
〔図A〕ASSPとASIC


