放熱,事後対策の進め方 ―― 温度分布や空気の流れの正確な把握と各種対策部品の使いこなしが鍵
● 空気の流れを可視化する
次に空気の流れを確認します.空気の流れを可視化するには,チョークの粉を使ってきょう体中の空気の流れの軌跡を残す方法,糸や毛糸を用いるタフト法などのさまざまな方法があります.
手軽な方法としては煙により空気の流れを可視化する方法があります.煙には入手しやすい線香などが一般的ですが,無害な炭酸ガスを大量に発生することができる専用のエアフロー・テスタ(写真4)を使用する方法もあります.写真5に実際の空気の流れを測定しているようすを示します.

写真4 エアフロー・テスタの例
米国Cambridge Accusenseの「FlowMarker」.

写真5 エアフロー測定のようす
● 空気の流れを最適化する
空気の流れの最適化に関して,ここでは要点を二つ説明します.
一つ目はきょう体の吸気口と排気口の最適化です.これらの位置,開口率(吸排気口の総面積のうち,穴の占める面積の比)などが,問題となっている部品に対して最適かどうかが重要なポイントになります.吸気口と排気口の位置は,本来なら初期設計の時点で最適化されていることが望ましく,また,きょう体の吸排気口位置の変更のような大規模な変更は試作機ができてしまった段階では受け入れられない可能性があります.
大規模な変更が受け入れられない場合,二つ目の方法として,
・対策が必要な発熱部品の位置を考慮して不要な吸排気口をふさぐ,あるいは開口率を調整する
・整流板を追加することで対策が必要な部品に対して空気の流れを集中させる(図1)
・きょう体内部に空気をかき回すためのファンを追加することで,きょう体内の空気の流れを改善する
といった方法を検討します.
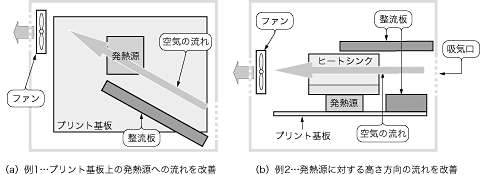
図1 整流板によるエアフロー改善例
空気の流れを集中させ,放熱効果を改善する.


