ソフト・マクロのCPUでLinuxを動かす(前編) ――FPGAベースのボード・コンピュータを設計する
● フリーI/Oピン
プリント基板は,サンハヤトのユニバーサル基板「ICB- 288」と同じサイズです.拡張用スルー・ホールの位置を合わせてあり,上下に重ねて使用しやすい形状としました(図6).
FPGAの未使用ピンのうちの84本を,フリーI/Oピンとして引き出しています.これは,FPGAのI/Oピンの数と基板外周に用意できる拡張用スルー・ホールの数から決定しました.I/Oピンのほかに,外部からの電源供給や制御,リセットを行うためのピンも用意しました.
ユーザI/Oは,汎用I/O機能として定義していません.したがって,使用するためには,所望の回路を設計する必要があります.このFPGAをカスタマイズするためには,MicroBlazeのライセンス(使用権)が必要になります.ライセンスはEDKを購入することで得られます.ロイヤリティ(LSIの個数に応じて支払う使用料金)は不要なので決して高価なものではありませんが,これまでソフトウェア開発を専業としてきたシステム・ハウスのように,FPGA開発に不慣れなケースも考えられます.そこで,汎用的に使えそうなさまざまなシステム構成をあらかじめ設計しておき,FPGAのコンフィグレーション・データとしてユーザに提供することが考えられます.また,カスタマイズを請け負うサービスも提供できます.
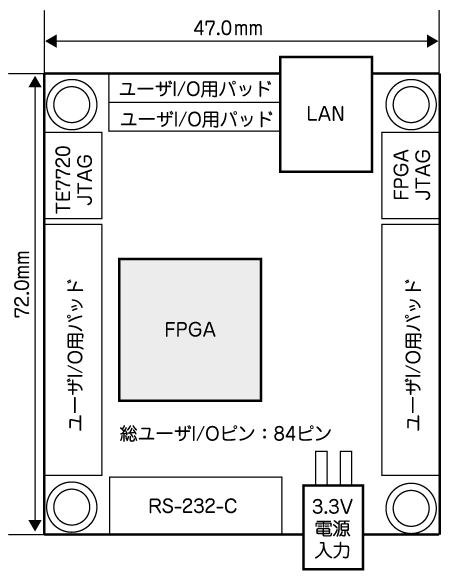
図6 プリント基板の形状と部品配置
外部回路を接続することを考慮し,サンハヤトのユニバーサル基板「ICB-288」と同じサイズにした.


