つながるワイヤレス通信機器の開発手法(7) ――続・原理設計を行う 通話の原理から通信を学ぶ
●通信には必要不可欠な「OSI 7階層モデル」
状態遷移やプロトコルで使われる無線チャネルのほかに,もう一つ呼制御に必要不可欠なものがある.それは,通信機能の階層構造(OSIモデル)である.
OSIモデルは,コンピュータ・ネットワークから派生したネットワーク・アーキテクチャの一種で,ISO(InternationalStandard Organization;国際標準規格)で規定された通信プロトコルの国際標準である.OSIモデルでは,音声などのさまざまなデータを送受信する場合に設計が楽になるように,機能ごとに七つの階層に分けている(図8).また,それぞれの階層に対して以下のような規定が定められている.
- 各階層とその上下の階層間のインターフェース
- 通信相手の同一層との通信プロトコル
これらの規定を守ることにより,ある階層の機能を追加・変更しても,上下の機能階層とのインターフェースには影響を与えない構成にすることができる.例えば,通信回線が固定回線であっても無線回線であっても,物理層でその違いを吸収してしまえば,それより上の層は通信回線の種類を考えずに構成できる.このため,再設計が必要な部分が減り,設計が楽になるというわけである.また,同一階層との通信プロトコルが規定されているため,上下の階層に依存しない設計とデバッグが可能となる.
例えば,PDC(Personal Digital Cellular)方式の回線制御のようすをOSIモデルで表すと,図9のようになる.この図からわかるように,基地局と回線網は物理層,データリンク層,ネットワーク層のみを通すパイプの働きをしており,それより上の層の機能は持たない.
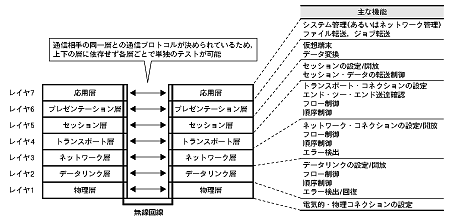
〔図8〕 OSI 7階層モデル
OSIモデルでは,音声などのさまざまなデータを送受信する場合に設計が楽になるように,機能ごとに七つの階層に分けている.
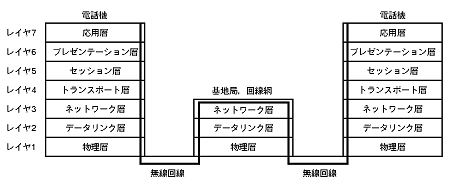
〔図9〕 PDC方式の回線制御のようす
基地局と回線網は,レイヤ4以上の機能を持たない.


