デバイス古今東西(28) ―― 現代の製造企業における内外作問題:半導体IPを事例として
現代の製造企業は,どこからどこまでを自社で行い,どこからどこまでを他社に頼むべきかという問題を抱えています.経済学的にいうと,自社の組織で行う(内作)か,市場から調達する(外作)かという問題です.早稲田大学 大学院商学研究所の黒須 誠治教授は,これを「内外作問題」と呼んでいます.
例えば,半導体開発であれば,設計情報の構築,製造,組み立て,テスト,販売のそれぞれで,自社の組織を使うか,市場を利用するかの選択があります.その中で半導体のIP(Intellectual Property)コア(本連載の第2回と第3回を参照)にこの問題を適用してみると,設計情報を内作するか,あるいは外作するかという選択になります.市場で売られていて安ければ,買ってくればよいことになります.しかし高ければ,あるいは市場で売られていなければ,自社の組織で開発することになります.その設計情報の構築に熟練技術が不要ならば,外部に委託することも考えられます.熟練が必要ならば,自社の組織内でその設計情報や知識を養成する必要が出てきます.
そもそも,内作と外作の相違点はどこにあるのでしょう.そして内作には,外作にはないメリットがあるはずですが,それは何でしょう.逆に外作が持つ,内作にはないメリットとは何でしょう.そして,内作か外作かを決定する要因として,何を考慮するべきでしょう.こうした問題を,半導体のIPコアを例にして考えてみましょう.
●内作/外作それぞれのメリットとデメリット
製造企業が半導体のIPコアについて内作か外作かを決定する要因を考える上で,必要な物や情報を考えてみます.まず,求める対象物が市場に存在するかどうかということを考える必要があります.市場に存在しなければ,自社の組織で作らなければなりません.もし自社の組織で作れば,設計情報,設計知識,ノウハウが蓄積されます.それらを次のプロジェクトに再利用できれば,開発期間を短縮できたり,コストを抑えることができます.これらの知的財産権(IP)を保有することになるので,社外に有償で使用権(ライセンス)を供与することも可能です.もしそのIPが特許のような他社にはない付加価値と競争力を持ち合わせているのなら,競合企業との差異化が図れるメリットがあります.
しかし内作にはデメリットもあります.内作を進めるならば,開発期間を考えなければなりません.製品の市場投入時期に遅れが生じるなら,経営上の利益を失う可能性が高まります(連載の第19回を参照).そして内作には成果物を作るための道具や環境が必要です.それらにはすべてコストがかかります.人件費などを含めると,場合によっては外作コストより高くつくかもしれません.さらに成果物ができたとしても性能が要求仕様を満足できない場合は,企業の競争力を失いかねません(連載の第10回を参照).
外作におけるメリットの一つは,多様なベンダから,その時その時の,最も低価格で競争力のあるコアの供給を受けられることです.開発期間の制約を受けにくく,市場投入の開始時期を早められるのならば,先行者利益が得られます.そして必要なIPコアの動作が試作チップ上であらかじめ確認されているのであれば安心して利用できます.つまり第三者のノウハウを利用することで,成果物の性能,および設計開発時間とコストの見積もり精度を高められるメリットがあるのです.
外作のデメリットは,調達前に仕様書を丹念に調査する必要があることです.要求仕様に欠けている部分は追加で修正してもらわなければなりません.そしてIPの統合化にはそれなりの技術ノウハウが求められます.積み木のようにブロックを組み上げれば済むものではありません.IPコア間のインターフェースをどうするのか,統合前後の検証をどうやったらよいのか,それらは自社で考えなければなりません.最後に使用許諾書の締結の問題があります.法務部を含めた社内外の作業は少なくありません.契約内の制約条件はビジネスに大きな影響を与えるものであれば問題になるので,慎重な精査が必要です.必然的に時間もかかります.
以上の議論から,自社の組織から見たIPコアの内作/外作のメリットとデメリットを整理しておきます(表1).
表1 IPコアの内作/外作のメリットとデメリット(製造企業から見た視点)
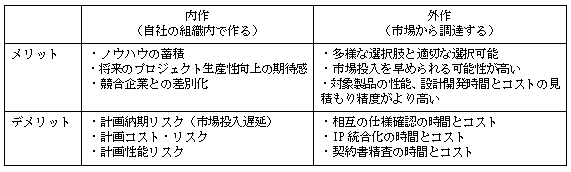
●決定要因はすべてコストに換算しうる
内作か外作かを決定する要因は,すべてコストというものさしに還元して検討することが可能です.上記のIPコアで考えると,情報コスト,内作コスト,外作コストに分類できます.コストは増加方向のプラスと低減方向のマイナスのそれぞれに働く力学を持ちます.
情報コストとは,市場にあるかどうかを探すための,そして市場にあった時にそれを探すためのコストです.内作コストとは,時間,経費,性能にかかわります.もう少し具体的に言うと,自社開発と設計の人的コスト,自社開発と設計に必要な道具や環境にかかわるコスト,自社開発と設計に必要な時間のコスト,熟練や改善による低減コスト,再利用による低減コスト,競争優位で授かる低減コストなどがあります.外作コストとは,市場に存在したとしたらその対価であり,市場投入を早められる低減コストを含みます.
●経済合理性のみでは決定できない場合も
内作か外作かを決定することは容易ではありません.内作と外作をコストの視点でバランス良く対比する方法は比較的分かりやすいかもしれません.ただし,経済合理性だけですべてが決まるわけではありません.例えば,経済合理性で選択すると外作になるところを,雇用を優先して内作する場合があります.
雇用問題がかかわる内外作の意思決定については,別途,機会を作って述べていきたいと思っています.
やまもと・やすし
◆筆者プロフィール◆
山本 靖(やまもと・やすし).半導体業界,ならびに半導体にかかわるソフトウェア産業で民間企業の経営管理に従事.1989年にVHDLの普及活動を行う.その後,日米で数々のベンチャ企業を設立し,経営責任者としてオペレーションを経験.日米ベンチャ企業の役員・顧問に就任し,経営戦略,製品設計,プロジェクト管理の指導を行っている.慶應義塾大学工学部卒,博士(学術)早稲田大学院.



Post a Comment