HDMI登場の背景と概要 ―― 映像インターフェースの推移から学ぶ
2.映像系のディジタル・インターフェース
実はHDMIが策定される以前より,映像系ディジタル・インターフェースとしていくつかの規格が存在し,その一部は市場で使われていました.HDMI誕生後も新しい映像系ディジタル・インターフェースが検討されています(表1).ここではHDMIとほかのインターフェースの特徴を比較することで,HDMIとの関係やHDMIの役割を確認したいと思います.
| 規格名 | 用途 | データ構造 | 音声伝送 | 最大ビット・レート |
| HDMI | CE | 非圧縮,ラスタ・スキャン | 可 | 3.4Gbps×6Line |
| i.LINK | CE | 圧縮,パケット | 可 | 400Mbps |
| DVI | パソコン | 非圧縮,ラスタ・スキャン | 不可 | 1.65Gbps×6Line |
| DisplayPort | パソコン | 非圧縮,スリム・パケット | 可 | 2.7Gbps×4Lane |
● i.LINKネットワーク環境と共存するHDMI
コンシューマ・エレクトロニクスの世界で映像系ディジタル・インターフェースといえば,最初にi.LINKを思い浮かべる方も多いでしょう.i.LINKが登場する以前は図3のように複数のケーブルでアナログ接続が必要でした.i.LINKは映像,音声,制御信号をケーブル1本で双方向ディジタル伝送が可能です.IEEE 1394をベースにしているので,図4のように機器をネットワーク接続できます.DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)が管理するDTCP(Digital Transmission Content Protection)方式による著作権保護機能を備えています.
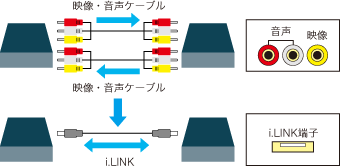
図3 i.LINK接続例1
i.LINKはケーブル1本で双方向通信を行える.
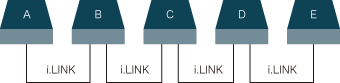
図4 i.LINK接続例2
従来のアナログ接続は1対1だったのに対し,i.LINKは複数台数をデイジ・チェーン接続可能.
これら基本的な機能を考えるとHDMIの用途はすでに市場に普及していたi.LINKと重複します.普通に考えれば映像系インターフェースのディジタル化はi.LINKで十分ということになるでしょう.しかしi.LINKにはいくつかの問題点がありました.
1)i.LINKは受信側にMPEGデコーダが必要
i.LINKはプロトコルにMPEG2-TSを採用しており,チューナから録画機器,あるいは録画機器間でのデータ転送に適しています.現在でも録画目的で使用が許された唯一の映像系ディジタル・ネットワークとして活躍しています.その反面,再生において受信側にもMPEGデコーダが必要になるという欠点がありました.
2)最大伝送速度400Mbpsとリアルタイム用途に不向き
i.LINKは,伝送レートが最大400Mbpsであり,圧縮伸張処理によってある程度遅延が発生します.リアルタイム性が求められるディスプレイ・インターフェースには適していませんでした.そのため,実際にi.LINK接続が普及したのは,主にDVHSとSTB(Set-top Box)/ディジタル・テレビ間の接続でした.D端子が使われていたSTB→ディジタル・テレビや,DVD→ディジタル・テレビ間の接続をディジタル化するためには,HDMIのような新しいインターフェースの登場が待望されていました.
3)ユーザがDVとの接続を確認する必要があった
i.LINKは運用面においても問題がありました.i.LINKはディジタル・ビデオ・カメラなどに搭載されていたDV方式を拡張したインターフェースです.しかしMPEG-2 TSを採用しているため,DV方式と互換性がありません.ユーザは接続の可否を確認する必要がありました(図5).
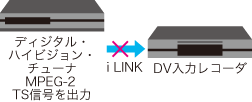
図5 i.LINKとDV方式
i.LINKとDV方式には互換性がないので,ディジタル・ビデオ・カメラなどの接続には注意が必要.


