初めてのETロボコン (3) ―― ゲリラ的豪雨ニモ負ケズ,試走会IIに臨む
●"難所攻略の試金石"試走会IIに臨む
モデルが完成し,モデル提出注4が終わった直後に待っているのは,2回目の試走会(試走会II)です.試走会IIは難所攻略の試金石とする予定でしたが,新ショートカット注5に対する特殊走行は実装(アイデア的なところも)が間に合わず,ゴール後停止注6とツイン・ループ攻略注7を試すことにしました.
注4;ETロボコンは,設計モデルと走行タイムの両方を競うロボット・コンテストである.設計モデルは「モデル部門」として,走行タイムは「競技部門」として別々に評価される.
注5;新ショート・カットとは,アウト・コースの一部に設けられた点線の近道コースである.ETロボコン2007までのコースに設置されていたショートカットと曲線の形状が異なるため,「新ショートカット」と呼ばれている.規定の方向で周回することで,ボーナス・ポイントが獲得できる.
注6;ゴール後停止とは,2周目のゴール・ライン通過後,一定の距離以内にロボットを停止させる技術である.ゴール後停止を実現できると競技規約によりボーナス・ポイントが獲得できる.
注7;ツイン・ループとは,名前の通り二つのループで構成されたコース区間である.規定の方向で周回することで,ボーナス・ポイントが獲得できる.
ゴール後停止については,試走会I以降,既にテスト・コースで試していたこともあり,良い感触はありました.またツイン・ループは後述のエッジ・チェンジという技術によって攻略可能で,これも既にテスト・コース上で実現していました.このため,楽観的に試走会IIに臨んだのですが...(写真1).

[写真1] 試走会IIの様子(撮影:吉澤姐)
ほかのチームの様子を見ているところ.
●坂の頂上にわなが!
まずはゴール後停止を試すために,ゴール手前の坂から走行させてみたのですが,うまくいきませんでした.現象は,坂の途中で停止してしまうというものでした.何度やっても,坂の途中で停止します.停止の条件は,坂の出口の灰色マーカを検知することにしていたので,どうやら坂の途中で灰色を検知してしまっているようです.
分析したところ,坂の頂上付近では光センサとラインとの距離が離れるため光センサに戻ってくる光の量が少なく,白が灰色に見えていたようです(図4).走行した軌跡は図5のようになっています.白を灰色と認識している間は左に操舵するので,ロボットは左に大きく蛇行します.その後,ラインに復帰するまでに黒の検知率がしきい値以下になったため誤検知となっていました.坂道は,コース上で唯一の立体区間であり,はまるべくしてはまってしまいました....
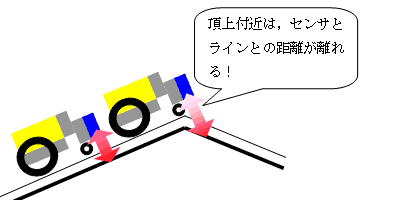
[図4] 坂の頂上付近を走行時の光センサとラインとの距離(横から見た頂上)
坂の頂上付近では光センサとラインとの距離が離れるため,白い部分が灰色に見えてしまうようだ.
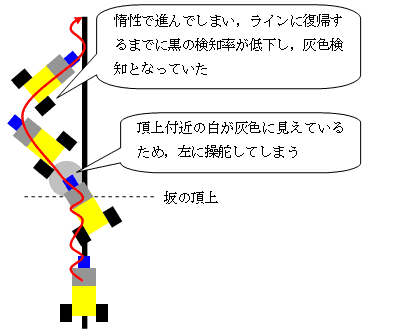
[図5] 坂の頂上付近の走行ラインと灰色誤検知(上から見た頂上)
坂の頂上で灰色を認識し,それに対応して動作するため,蛇行して停止する,という挙動になっていた.
●坂の出口にもわなが!
ひとまず,「坂の頂上にも灰色マーカがある」という形でプログラムを暫定的に修正しました.これでようやくゴール後停止が実現! と思ったのですが.またもやうまくいきませんでした(写真2).現象は,坂の出口の灰色マーカを通過後も停止しないというものです.何度やっても停止しません.

[写真2] 坂の出口の灰色マーカに苦しむ(撮影:吉澤姐)
停止の条件は,坂の出口にある灰色マーカを検知することなので,どうやら今度は坂の出口の灰色マーカを検知していないようです.分析したところ,坂の出口の灰色マーカは短く(コース上で最短の100mm!),しかも通過時は下り坂により速度が速くなっているため,しきい値まで黒の検知率が低下していないようです(図6).しきい値を高めに&サンプリング数を少なめに設定すれば検知できそうですが,そうすると他所での誤検知の確率も上がるので,悩みどころです.
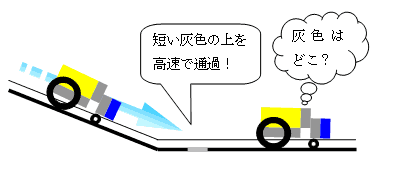
[図6] 坂の出口の灰色は短い
かつ,通過時の速度は速い....


