Twitterを使って技術系コミュニティを立ち上げよう!(4) ―― Twitterが開く技術系コミュニティの世界
前回は,Twitterで偶然出会ったつぶやきがきっかけで,MATLABコンテストや「集合知」という新たな観点が生まれ,当初は想定していなかった展開が始まりつつあるというお話を紹介しました.今回は,Twitterを通して学んだ体験を元に,技術系コミュニティ立ち上げの可能性について考察したいと思います.
●MathWorksが考えるもう一つのメガトレンド
MATLAB EXPO 2009の基調講演で,MathWorks社長のJack Littleは当社が注目する技術革新のメガトレンドとMathWorksの取り組みについて紹介しました(図1).実はもう一つ,時間の都合で語られなかったメガトレンドがあります.
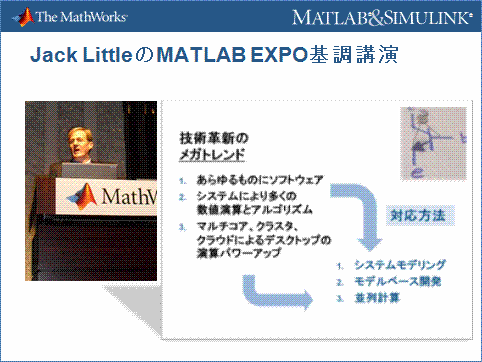
図1 MathWorksが注目する技術革新のメガトレンド
近年,MixiやFacebookのようなSNSなどに代表される新世代のWebサービスが登場したことにより,人間の社会行動とコンピュータが今まで以上に密接にかかわるようになってきました.また,ウィキペディアやMATLABコンテストの事例のように,こうした技術が新たな知的生産の枠組みを提供する可能性が生まれています.MathWorksではこれを一過性のブームではなく,技術革新のメガトレンドの一つとしてとらえ,Social Computingと呼んでいます(図2).
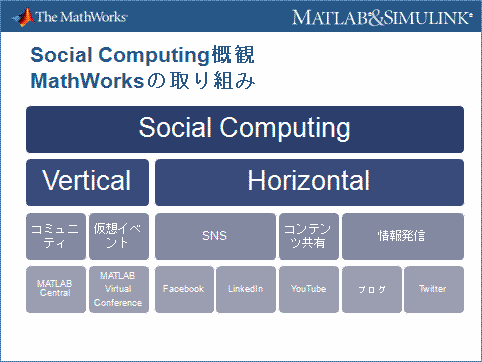
図2 もうひとつのメガトレンド,Social Computing
●なぜMATLAB EXPOにTwitterを持ち込もうと思ったのか
MathWorksはさまざまな形でSocial Computingに取り組んできました.2001年にはcomp.soft-sys.matlabニュースグループを発展させる形でMATLAB Centralを立ち上げました.MathWorks製品の開発エンジニアによる公式ブログは2004年から,YouTubeは2006年から,Facebookも2007年から始めています(図3.最近の例としては,社屋増築竣工イベントで使用した石弓の写真をFacebookに掲載した).さらに2009年からは,MATLAB Virtual Conferenceなどの仮想イベントも本格的に開催してきました.しかし,Twitterについては,MATLAB EXPO以前はRSSのように一方的に最新情報を発信するような使い方しかしていませんでした.

図3 FacebookのMATLABページ
日本でSocial Computingの取り組みを始めるにあたり,MATLAB EXPOというライブ・イベントと組み合わせる形でTwitterを採用した背景には,日本の文化的特性への配慮があります.海外では,純粋にオンラインだけで成立しているコミュニティは多々ありますが,日本で成功している事例の多くは,実際に顔合わせする機会のある団体活動の延長として,オンライン・コミュニティが形成されているようです.
一つの仮説ですが,こうした違いの背景には,コミュニケーション・スタイルの違いがあるのではないかと思います.一般的に,コミュニケーションは言葉で語られる以上に身振り手振りや表情などが重要になります.日本人の場合,特にこの非言語的要素の比重が大きいため,顔合わせをする機会が健全なコミュニケーションを維持する上で必要度が高いのではないかと考えています(図4).
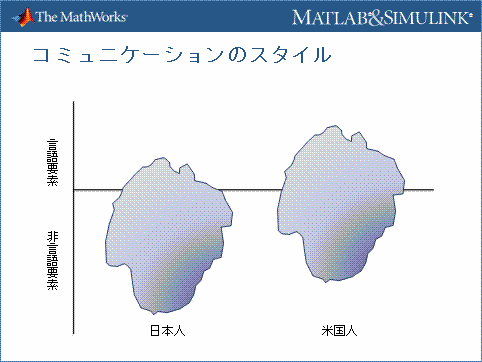
図4 コミュニケーションにおける言語要素の重要度は文化によって異なる


