安全に対する意識を高め,機能安全のスタート地点に立とう ―― 『自動車と機能安全』
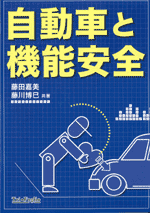 | 『自動車と機能安全』 |
近年,電気・電子系システムの故障が原因となる事故が増加しています.この問題への対策として,欧州を中心に策定されたのが機能安全規格です.2000年以降,各産業分野向けの機能安全規格が立て続けに発行され,自動車産業における機能安全規格「ISO 26262」も2010年に正式発行予定となっています.自動車業界は,今まさに,機能安全対応をどのように進めていけばよいのかという準備に追われている状況です.
システムの故障は,設計ミスやコミュニケーション・ミス,スキル不足など,主に個人や組織の問題によって生じる「決定論的原因故障」と,部品の劣化によって生じる「ランダム・ハードウェア故障」に大別できます.機能安全は,これら両方の故障を削減するための方策になっています.前者への対策としては,設計やテスト,コミュニケーション,文書管理のやり方などをより厳密に規定し明確にすることで対応します.また後者に対しては,多重化,多様化した設計を行うことで1カ所が壊れても稼動可能にしたり,故障検出機能を搭載することで故障しても安全側に動作するように設計するなどの方法で対応します.
欧州は規格への対応要求が非常に厳しい地域です.例えば,産業機械分野では,制御システムの機能安全規格であるEN ISO 13849への対応が必須です.対応していない製品は,2012年以降,欧州で販売できない恐れがあると言われています.自動車を含むほかの産業分野においても同じことが起こる可能性があり,各社が早めの対応を検討しているところです.
本書は,自動車の機能安全を始める際に,スタート地点に立つには良い本です.自動車の機能安全対応を行う上で必要とされる以下の情報が,1冊にまとめられています.
- 機能安全が必要とされている背景
- 安全規格が作られた背景
- 関連する安全規格の説明
- 日欧米の安全に対する考え方の比較
- 重大事故や自動車のリコールに関する具体的な事例紹介
- 品質管理,品質改善(ISO9000,CMM,AutomotiveSPICEなど)
- 自動車システムの紹介
- 車載ソフトウェアの問題点
- 自動車業界の最新動向の紹介
また,ところどころ「1口メモ」として具体的な解説があるので,イメージしやすくなっています.機能安全規格は抽象的な部分が多く,規格要求の解釈が非常に難しいため,具体的な解説が助けになります.
しかし残念ながら,全般的に自動車業界の動向や品質管理の紹介が多く,機能安全に特化した説明が少ないように思います.そのため,
- 機能安全対応のために何をすればよいのか?
- どうすれば機能安全認証を取得できるのか?
といった,機能安全の取り組みを始めたばかりの方が知りたい道筋について,具体的な答えが書かれていません.先ほども述べたように,今は自動車業界の多くの会社が,現プロセスに機能安全をうまく取り込むにはどうすればよいのかを検討している段階です.「良いやり方」を知りたいのですが,残念ながらその答えは,本書には載っていません.
評者自身も,2006年より機能安全対応システムの開発や支援を行ってきました.その結果,評者の会社は,日本初の機能安全対応プロセス認証を取得することができました.この経験より,機能安全対応の難しさは,
- 規格の肝を理解すること
- その上で,効率的に安全性を向上させること
- 従来よりも作業量が増えた分を,ツールなどを導入していかに効率性を上げるか
といったところにあると考えています.
これらのノウハウは,認証機関自身もしくは実際に機能安全認証取得に取り組んできた会社しか持っていません.本書の筆者には,機能安全認証を取得するための大変な苦労を伴う開発経験がないように思われます.そのため,具体的な対応方法について書かれていないのでしょう.
しかし,機能安全の一番の基本は「安全に対する意識」です.安全意識を持たずに,覚えた手順どおりに作業しても,工数や手間が増えるだけで,安全性は上がりません.機能安全では,安全意識を持った上で,重要なポイントを押さえつつ作業することに意味があります.
本書を読めば,重大事故や安全規格の紹介を通して,安全に関する意識を向上することができるでしょう.また,自動車に関するさまざまな情報がまとめられています.そのため,自動車の機能安全に取り組むためのスタート地点に立つには,良い本だと思います.
もりかわ・あきひさ
(株)ヴィッツ


