暮らしに役立つQC七つ道具(5) ―― 散布図:「傾向」を「推理」する
パレート図,ヒストグラム,散布図と,ここ3回はグラフについて説明してきました.ここで,グラフに関しても少し説明しましょう.
解析にグラフを使う目的は,問題の「見える化」です.グラフにすることで,データを見るだけでは分かりにくかった問題を「一目瞭然」にすることができます.
グラフは,折れ線グラフ,棒グラフ,円グラフ,といったものが代表的です.そのほかにも,レーダ・チャートやガント・チャートなどいろいろなものがありますが,基本的な種類のグラフとその特徴を覚えておくと,さまざまな分析ができるようになります.
以下は,典型的なグラフとその特徴です.
| グラフ | 特徴 |
| 折れ線グラフ | 数量の変化を見る |
| 棒グラフ,体積グラフ,面積グラフ | 数量の大小を見る |
| 円グラフ,帯グラフ | 各項目の割合を見る |
| レーダ・チャート | 全体像の把握 |
| ガント・チャート | 状況の把握 |
●月末になるとお金が足りなくなってしまう原因は?
さて,それでは例題を考えてみましょう.
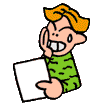 Z(ツェット)くんは,困っています.
Z(ツェット)くんは,困っています.なぜか,いつも月末になるとお金が足りなくなってしまうのです.貯金もしたいのですが,今のままではとてもできません.特に無駄遣いをしているつもりもないのに,どうしてお金が足りなくなってしまうのか,分からないのです.
散布図は,問題がどこにあるのか,ある程度目星がついてきたときに使うことが有効なので,ほかのQC七つ道具と組み合わせて使うことにしましょう.
- まず,パレート図やチェック・シートを使って問題のありそうな項目を見つけます.
- その問題が何の「要因」で起きているのか,「仮説」を立てます.
- その「仮説」に基づいて,二つの項目を対にしてデータを取り,散布図を書いて「仮説」が正しそうなのかどうかを調べます.
- 相関が認められない場合には,また別の「仮説」を立て,散布図を書いて「仮説」を検証する,ということを繰り返します.
例えば,趣味に使うお金に問題がありそうだったとします.給料が出た直後に,気が大きくなって使いすぎてしまっているのではないかという「仮説」を立てたとしましょう.その場合,給料日からの日数と趣味に使った金額を対にしたデータを作成して,相関があるのかどうかを散布図にして確認します.
思っていたとおりの相関が出てくるようであれば,「対策」を考えます.逆に,思っていたのと異なる結果が出た場合には,見落としている「要因」があるということなので,また別の角度から「仮説」を立てるようにします.
Zくんは,給料が出た後の自動車関係のお金の使い方に相関がないか調べてみることにしました.
すると,どうやら正の相関が成り立っているようです.
Z:「どうも給料の出た後に近いほどお金を使っているみたいだ.こうしてみると,長距離ドライブなんかは,給料日のすぐ後に行っているんだろうな.それに給料日直前はやっぱり使っていないな.(^^;
余っているお金を全部車につぎこんでいるような気がするなぁ.うーん... なんか対策を考えよう」
* * *
次回は「特性要因図」を取り上げます.お楽しみに.(^ ^)
*参考文献:不透明な時代を見抜く「統計思考力」神永正博 著
くにひろ・よういち
◆筆者プロフィール◆ 国広 洋一(くにひろ・よういち).東京多摩在住の組み込み系ツール企業勤務エンジニア.『基本から学ぶソフトウェアテスト
国広 洋一(くにひろ・よういち).東京多摩在住の組み込み系ツール企業勤務エンジニア.『基本から学ぶソフトウェアテスト』の勉強会に参加したことをきっかけに,社外の勉強会にときおり参加しています.TEF(Testing Engineer's Forum;ソフトウェアテスト技術者交流会)やSQiP(Software Quality Profession,スキップと発音する)の勉強会に行くと会えるかも.TestLink日本語化部会のメンバでもあります.オープン・ソースのテスト管理ツールであるTestLinkをどうぞよろしく.


