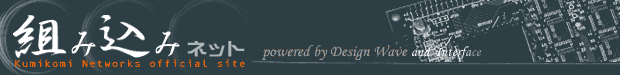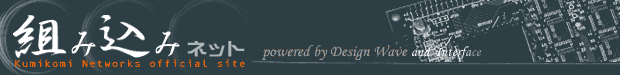|
|
A-1 SH2&V850付属基板対応拡張ベースボード
11:00-11:30 [村上 真紀/CQ出版(株) Interface編集部]
|
|
|
A-2 Windows Vista時代のデバイス・ドライバ開発
12:00-12:30 [日高亜友/(株)デバイスドライバーズ]
Windows Vistaの導入とともに,Windows用デバイス・ドライバの開発キットが新しくWDKになりました.ここではドライバ開発に関連するWindows Vistaの新機能,WDKの概要と,Windows NT以来初めて投入されたデバイスドライバ開発用フレームワークのほか,Eclipseを使ったWindowsデバイス・ドライバ開発デモを紹介します.
|
|
A-3 μT-Kernelとは何か? 活用法を解説
13:00-13:30 [由良修二/T-Engineフォーラム]
始めに「μT-Kernelの概略」と題して,T-KernelやμITRONとの違い,登場の背景,設計方針について説明します.続いて,μT-Kernelのリファレンスコードを入手してからターゲットボード(μTeaboard)で動作させるまでの手順の概略について説明します.
|
|
A-4 FPGAのデバッグ環境と効率化のテクニック
14:00-14:30 [畑山 仁/日本テクトロニクス(株)]
画像処理や通信などのFPGAの設計では,シミュレーションよりも実システム内で設計検証およびデバッグした方が効率的です.そのためにFPGAベンダや計測器ベンダが用意しているさまざまな手段についてご紹介します.
|
|
A-5 組み込みデータベース・プログラミング入門
15:00-15:30 [高橋君夫/エンサーク(株)]
データ量やデータ項目の増大などの原因から,さまざまなデバイスを使って効率良くデータを扱うためにデータベースが利用され始めています.その中で「データ検索」だけでなく,多様化する仕向け地向けの言語対応や画面遷移の管理にデータベースを利用し,開発の効率化を行う手法・事例をご紹介します.
|
|
A-6 FPGA+ソフトウェア・コアCPUでμClinuxを
活用する
16:00-16:30 [福島雅史/東京計器工業(株)]
組み込みOSを活用する場合,デバイスドライバやアプリケーションの開発は必須です.本講演では,μClinuxを使ってデバイス・ドライバの開発やμClinux上で動作するアプリケーションの開発,ならびにカーネル・デバッグとアプリケーション・デバッグの違いについて事例をもとに解説します.
|
|
|
|
B-1 気づけるエンジニアを育ててみる
11:00-11:30 [宿口雅弘/三菱電機マイコン機器ソフトウエア(株)
技術企画センター 主査,「元気なら組込みシステム
技術者の養成」プロジェクト カリキュラム委員]
コンピュータ知識のほかに,対応するシステム・ドメインの知識が要求される組込みシステムに携わるエンジニアの教育が叫ばれています.さまざまな解決の試みが各地や各社,各団体でなされており,成果が報告されています.その一方で,エンジニアに自ら問題を分析し解決できる力を求める声も大きいです.自立(自律)するために“「気づける」には?”を課題として取り組んだ試みを紹介します.
|
|
B-2 MATLAB/Simulinkを利用したVサイクル開発
12:00-12:30 [城所 仁/dSPACE Japan(株)]
|
|
B-3 Xilinx MicroBlazeの長所を120%引き出す
13:00-13:30 [実吉智裕/(株)アットマークテクノ] |
|
B-4 「組込みソフトウェア技術者試験 クラス2」
の傾向と対策
14:00-14:30 [久保幸夫] |
|
B-5 デザイン・レビューの勧め
〜設計工程の後戻りを最小限に抑えるには〜
15:00-15:30 [浅井 剛/東京計器工業(株)]
システム開発において,不良を次の工程に持ち越さないのは常識です.しかし開発対象が大きくなるにつれて分業化が進み,小規模な範囲のバグ出し(品質)は担当者に一任されて入ることが多いです.その結果,思い込みや勘違いによる不良が見逃されて後戻りが多く発生し,検証工数の増大の一因となっています.不良による設計工程の後戻りを最小限に抑えるデザインレビューの重要性について解説します.
|
|
B-6 マルチコア環境におけるタスク設計検証
16:00-16:30 [藤倉俊幸/イーソル(株)]
タスク設計に形式的手法(主にCSP)を導入することで,シングル・コアでもマルチコアでも環境を選ばず設計・検証が出来るようになりました.検証をしない今のアーキテクチャ(タスク設計)はほとんどがデタラメで話にならないことが分かりました.この技術の特徴の一つは,アプリケーションの動作から設計・検証に入るところです.そのあとRTOSにマッピングを行います.この際,マッピング先はRTOSでなくていいです.その視点から見ると,汎用RTOSの時代は終わったと言えます.ITRONは無用の長物でしょうか.CSPはトランスピュータと共にほとんど死に掛けていた技術です.なぜ良い技術は滅びるのか,必須な技術を持ったエンジニアが冷遇されるのか,今後の技術の行く末について考察します.
|
|
B-7 [ETフェスタ] BLANCA開発者&ユーザ座談会
17:00-17:30
現在開発中のBLANCA“おもしろ”応用事例のデモンストレーション(昔懐かしのあの曲がよみがえる! そんな簡単な回路でTV出力が!? ポータブルBLANCA? レガシー・インターフェース復活計画? ほか)や,BLANCA開発者をまじえての意見交換&座談会を開催!
BLANCAユーザもそうでない人でも,「BLANCAでこんなことができないか」「あんなことができないか」と,開発筆者陣にあなたのアイデアをぶつけてください!!
|
|
|
|
C-1 2007年7月号 Design Wave Magazine付属
FPGAボードで試すソフトウェア・ラジオ
11:00-11:30 [林 輝彦/(株)ソリトンシステムズ]
組み込みシステムの実験に2007年7月号 Design Wave Magazine付属の実験基板が有効に活用できます.高周波信号をただちにAD変換し、受信機としての信号処理の大部分をディジタル,ソフトウェア処理するDDC(デジタル・ダウンコンバータ)構成のソフト・ウェアラジオを,DWM 7月号に付属したFPGA基板(25万ゲート相当)に実装した例を紹介します.
|
|
C-2 マルチコア・プログラミングの基礎と
RPCベース手法
12:00-12:30 [須賀 敦浩,鈴木 貴久/(株)富士通研究所] |
|
C-3 ここから始めるUMLモデリング
13:00-13:30 [照井康真/(株)テクノロジックアート UMLモデリンググループ]
大規模化,複雑化する組み込みシステム開発において,IT系のシステム開発で広く普及している汎用のモデリング記法,UML(Unified Modeling Language)を導入する動きが進んでいます.本講演では「本来のモデルとは何か」という本質的な理解を助けるとともに,UMLによる整理法を解説します.
|
|
C-4 PHS経由でネット接続可能な
Ethernetアダプタをハック
14:00-14:30 [中本伸一/(有)サイレントシステム エクゼクティブエンジニア] |
|
C-5 16ビットPICマイコンのアーキテクチャ
15:00-15:30 [後閑哲也/(有)マイクロチップ・デザインラボ]
マイクロチップ・テクノロジー.ジャパン(株)から発売された16ビットPICマイコンの「少ピンPIC24シリーズ」の特徴とアーキテクチャについて解説します.このシリーズは100ピンのデバイスと同じ内容の周辺モジュールを内蔵しており,ピン割り付け機能によって少ないピン数でも豊富なモジュールを有効活用できます.
|
|
C-6 CQ組込み機器開発システムによる
システム開発事例
16:00-16:30 [井倉将実/来栖川電工(有)]
BLANCA向けの組込プロセッサとして,XILINX(株)はMicroBlazeを標準で用意しているが,そのほかにもルネサス テクノロジのSH4aやアナログ・デバイセズ(株)のBlackFIN,フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン(株)のPowerPC,そして新たに日本アルテラ(株)のNIOS-IIが用意された.筆者はルネサス テクノロジのSH4aボートの開発から生産までを担当している.SH4aとBLANCAを組み合わせたシステムの応用事例についてや,組み込みシステム機器開発における設計の留意点を紹介します.
|
|